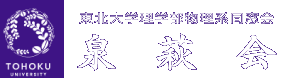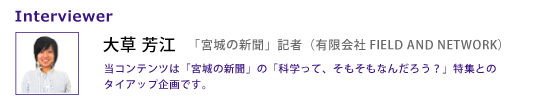活躍する泉萩会会員
野家 啓一さん
1949年仙台生まれ。宮城県仙台第一高等学校卒業、東北大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院科学史・科学基礎論博士課程中退。南山大学専任講師、プリンストン大学客員研究員などを経て現在、東北大学文学部教授。専攻は科学哲学、言語哲学。近代科学の成立と展開のプロセスを、科学方法論の変遷や理論転換の構造などに焦点を合わせて研究している。また、フッサールの現象学とウィトゲンシュタインの後期哲学との方法的対話を試みている。主な著書に、『言語行為の現象学』『無根拠からの出発』(以上、勁草書房)、『物語の哲学』(岩波現代文庫)、『科学の解釈学』(ちくま学芸文庫)、『パラダイムとは何か』(講談社学術文庫)など、多数。1994年第20回山崎賞受賞。
今回訪問したOBは、S46年物理学科卒の野家啓一さん。野家さんは東北大学理学部物理学科をご卒業後、哲学に転向され、現在は東北大学大学院文学研究科・文学部教授として、科学哲学と言語哲学を専攻されています。野家さんへのインタビューを通して、理学部物理系同窓生の活躍をご紹介します。
―野家さんは東北大学理学部物理学科をご卒業後、哲学に転向されていますが、
野家さんが科学哲学を選んだ理由を教えてください。
今から振り返れば、何らかの意味では、昔から科学や哲学への関心を持っていたのだと思います。
科学に興味を持ったのは、ジョージ・ガモフ(1904-1968)の『1,2,3...無限大』という本を中学のときに友達から借りて読んだのが、きっかけでした。
相対性理論や量子力学などの話題が、青少年向けに解りやすく解説されており、科学に対する興味をかきたてられました。物理学を学べば、宇宙の謎がすべて解けるのではないか。
ガモフ全集10巻を読んでそう思い、物理をやろうと目標を定め、東北大学理学部物理学科へ入りました。
ガモフ全集は現代科学の最先端の動きを伝えてくれると同時に、今思えば、哲学的なものの見方、私が惹かれたのはそういうところでした。
物理学を学べば、時間とは何か、空間とは何か、宇宙の果てはあるのかなどが、わかるのではないかと思い物理学科に入りましたが、実際の物理は実験などの現場仕事が中心で、
自分がイメージしていた物理学と現場の物理学の間にギャップを感じました。
さらに1960年代から1970年代は大学紛争の真っ只中。
そして公害が社会問題化していた時代でしたので、
科学と社会の関わり方、科学のあり方を考えざるを得なくなりました。
そういうところから次第に、物理学そのものよりも、
物理学的な考えのしくみや、社会に与える影響、つまりは科学史や科学哲学という方向へ
関心が次第にシフトしていったのです。
―野家さんのアプローチ方法とは、どのようなものですか?
ひとつは、「分析哲学」とも言われますが、言葉や論理を手がかりにすることです。
論理学(logic)の語源はギリシャ語で「logos(ロゴス)」と言い、
これは宇宙を支配している法則をも意味します。
「はじめに言葉(ロゴス)ありき」と新約聖書「ヨハネ伝」の冒頭の文章にもありますが、
ロゴスは言葉や論理であると共に宇宙の秩序でもあり、手で掴めるものではありません。
けれども概念や観念というものは言葉を通じて操作されるもので、
概念を組み換えて新しい思考形態をつくりだしていくのですから、
ものの見方・考え方と、言葉の働きには密接な関わりあいがあります。
大森荘蔵さん(野家さんが東京大学大学院時代に師事)の影響もあって、
言葉を分析することを通じて、概念、事物あり方、ものの見方・考え方、理論のしくみを
追求していく方向へと進んでいきました。
―そもそも、ものの見方・考え方は、すべて言葉となるものなのでしょうか?
核となる言葉による理解ですが、もちろん言葉にはならない直感的把握も重要な役割を果たしています。
そういうところは、言葉だけでなく、身体で認識しています。
物理化学者であると同時に科学哲学者だったマイケル・ポランニー(1891-1976)は、
それを「暗黙知」と呼んでいます。暗黙知とは、ポランニーによれば「我々は言葉にできることよりも多くのことを知ることができる」というこことです。
例えば、自転車に乗れるけれども、その乗り方を言葉で説明することはできません。
反対に言葉で説明されても、自転車に乗れるわけではありません。水泳なども同じですが、体で覚える部分はあるわけです。
哲学者のギルバート・ライル(1900-1976)も、
それをknowing thatとknowing howと区別して呼んでいます。
言葉で説明してもわからない。
けれども実際にやってみたりすることで理解できるし、可能になること。
そういう側面のことです。
ですから、私はこれまで言葉になる部分を追求してきましたが、
科学の中にも、実験操作を通じて、体で覚えていくとわかる部分があるのは確実なことです。
その両側面を押さえていなければ、科学の本質はわからないでしょう。
もうひとつは、最近、遺伝子組み換え食品の安全性やBSE問題などがありましたが、
科学者が理論的に説明する「安全」という概念と、市民が「安心」して食べられるという概念の間には、
ギャップがありますね。
科学者が説明して「安全」だというのと、
それでも「口に入れるものなので何となく嫌だな」という市民の感覚。
科学的合理性からは「安全」だとわかっていても、
社会的な合理性から見ると「安心」できないというところがあって、
そういう意味では、科学と社会の間に、ある種のギャップがあります。
そのことも、単なる頭だけの知識として科学を理解するのではなくて、
身体感覚として「おかしい、嫌だ」と感じるものがあった上で、
科学的な合理性とすり合わせていくことが、
科学の側にも、社会の側にも求められていくのだろうと思います。
―もともと科学的な合理性とは、ある前提のもとに言えることだと思うのですが、
細分化された今の社会ではその前提を感じづらく、科学を相対化する機会が少ないと感じています。
科学というのは、ある前提のもとで行われている知的作業です。
実験室のミリグラム単位の物質が市場に出て、社会の中で流通しだすと何トンも蓄積されるわけです。
けれども科学者が頭の中で考えるのは、ミリグラム単位。
その物質が何トンも社会に放出されたとき、どうなるかについては余り考えもしない。
昔は、実験室でつくられたものが、市場にすぐに出まわることはありませんでした。
実験室で発見された成果が実用化され、
何ステップかを経て市場に出回ることになるまでは、それなりの時間がかかったのです。
その間に、社会的な影響に対する議論を行う時間も充分に持てたわけです。
しかしながら科学技術の発展によって、実験室でできたものが、
市場に出されるサイクルが今は極端に短くなっています。
食卓と実験室が地続きになってしまいました。
これからは、どうすれば安全と安心をつなぐ回路、
つまり科学と社会の間に「実験室と社会をつなぐ回路」を見つけられるかが重要な課題になってきています。
そのときに、最後に頼りになるのは、市民の身体感覚、つまり暗黙知が重要になるでしょう。
普通、昆虫や蛇を食えといわれれば、躊躇しますよね。
身体感覚は、もちろん飢えれば食いますので絶対的なものではありませんが。
虫酒や蛇酒は美味しいらしいですけどね(笑)。
今はその身体感覚を超えて、技術的な進歩が早いから、
さまざまなアレルギーや新型インフルエンザなど身体が対応できなくなっている。
そのような状況だからこそ、逆に身体感覚を大切にしなければならないと思います。
身体感覚も脳科学で解明できるのかもしれないけど、
脳科学で解明できたからって、蛇が好きになるわけではないですからね。
―科学と人間の身体感覚との乖離が社会に与える影響とは、どのようなものでしょうか?
科学は、論証と実験の二つの要素で成り立っています。
論証は頭の中で操作できるけど、
実験は実際にやってみて、具体的なものから抵抗を受けながらやるわけですね。
そのときには、こうすればこうなると思っても、うまくいかないことがあります。
近代科学の中核にある構成的実験とは、余計な要素は切り捨てて、理想的な条件のもとで必要な要素だけを取り出して操作することです。
自然はそのままではとても複雑ですから、単純に要素だけ取り出すことはできませんが、
科学はできるだけ単純な要素に分解して、人間の認識にとって必要なものを取り出しています。
一方、身体は自然が持っている複雑さを同時に持っています。
自然を相手にするにしても、科学はできるだけ対象を単純化しようとしていますが、
自然は変化し続けているので、複雑さを片方に置いておかないと、
自然を単純化しすぎて、人間の都合にひきつけすぎてしまうのではないでしょうか。
例えば医学で言うと、病気は治ったけれども患者は死んだということになりかねない。
また、生態系の破壊や環境汚染などが生じてしまう。
自然の複雑さをもういっぺん、身体で感じ取りつつ、その条件を単純化することが大切です。
そのあたりが、実験室での操作は、余計な要素を取り除いて、自然を純粋化することですが、
純粋化された自然が本当の自然だと思い込む錯覚があるように思います。
実際の自然は、色々な条件が絡まりあっています。
レイチェル・カーソン(1907年-1964)が『沈黙の春』で告発したDDTは、
非常に有効な農薬でした。
DDTは、害虫を取り除くという意味では有益な農薬です。
けれども害虫というのは、人間にとって、勝手に害だとか益だとか言っているもので、昆虫にはあずかり知らぬことです。
では害虫を殺せばいいのかと言えば、それで生態系のサイクルが狂ってしまうわけです。
木を見て森を見ない。
細分化は学問の発達にとって必要なことですが、科学が細分化されるにしたがって、
私たちは自然を全体として相手にしていることを忘れがちです。
すると良いと思ってしたことが、結果として最悪な事態を起こすことになりかねません。
実験室において、法則なり新物質なりを取り出すために、
対象を細分化して、機器に閉じ込めて、条件を純粋化するにしたがって、
全体の自然を切り取って操作していることを忘れがちになるということですね。
環境問題、食糧問題、温暖化問題、エネルギー問題など、
人間が、これまで細分化的な方法でやってきたところが、全体のバランスが崩れ、コントロールできないことになっています。
これらの問題は技術的に解決できると考える人がいるけれども、
私はそれは楽観的過ぎると思っています。
もちろん、対症療法的な方法として技術的な進歩もあるでしょうが、
それがまた別の副作用を起こすことがあり得ます。
自然の全体像を人間はある意味、忘れてきました。
細分化して分析する方向のみ進んできたので、全体のバランス感覚を失いかけています。
しかし、新たなものごとに出会ったときに、嫌だなと不愉快に感じる身体センサーが
人間にはもともと備わっています。
賞味期限間近になっている食べ物も、匂いを嗅いでみて、
腐っているようだったら食べないでしょう。
元々人間にはセンサーが備わっているので、賞味期限などの文字に惑わされるよりは、
身体感覚を信じたほうが良い。
ですから害になる食べ物かそうでないかは、文字に書いてある何月何月が重要なのではなくて、
自分で匂いを嗅いだり味をみり、身体感覚で確かめた方が、はるかに確実だと思います。
お腹を少々壊しても、別に死ぬわけではないでしょうから。
―本来備わっているはずのセンサーも、使わなければ全体像を感じられなくなるでしょうか?
使わなければセンサーは摩滅していくのではないでしょうか。
歩かなければ足の筋肉が弱るのと同じです。
人間は、正確にものごとを把握しようと、あらゆることを数値化してきました。
しかしながら数値に頼って、もともと持っていた人間の感覚が、
その能力を使わなかったために、退化していると思いますけどね。
学生時代、私はワンダーフォーゲル部でした。
山に登ると、頭で考えたことは役に立ちません。
もちろん考えはするけど、現場に立ってみないとわからないことがある。
やはり本で読んだことでわかるのではなくて、実際に体験することでわかってくるし、
感覚を研ぎ澄ますことができます。山に登って天候の変化や岩場の危険を感じる、そういう感覚です。
最近はカーナビもありますから、方向を確かめる必要がなくなりました。
すると、方向感覚も退化していきます。昔は、北極星を頼りに旅をしてきたわけですからね。
技術的には発展して、人間は余計な能力を使う必要がなくなったけど、
身体感覚は退化して、生きる力、サバイバル能力を下げているのではないかと思います。
―哲学という立場は、科学を一歩ひいたところから捉えることができるのですね。
科学と社会の関係性というように。
一歩退いた立場で見ないと、その中にどっぷり漬かったのでは、見えるものも見えなくなると思いますね。
―では現場の科学者が、社会とのつながりをもつことは、難しいことなのでしょうか?
最先端の現場から、一歩ひくことは難しいことだと思います。
けれども思想家の吉本隆明(1924-:作家のよしもとばななの父)が次のようなことを言ってました。
外界を知らないという意味の「井の中の蛙」という表現がありますが、
「井の中の蛙」だって、自分が井戸の中の蛙であることを認識すれば、
井戸の外に出ることをしないでも、外部の世界とつながることができる。
ですからその言葉を借りるとするならば、科学と社会のあり方を考えるときに、
科学の外に出る必要はなくて、科学は社会の中のひとつの活動であることを把握すれば、
社会とつながることができると、言い換えることができるでしょう。
―最近、市民に対する科学への理解増進活動が活発になったと感じますが、
同時に、科学者自身も科学は社会の中のひとつであることを把握すべき、
という意図もあるのでしょうか?
おそらく表裏一体であると思います。
もちろん一般市民や文系の学生が、「科学技術リテラシー」を身につけることは必要不可欠です。
例えば、原発の話でも、放射能の半減期を知らなければ、賛成も反対もできませんし、
遺伝子組み換え食品の安全性を論ずるのなら、分子生物学の初歩を知らないと、議論にはなりません。
その一方で、科学者や理系の学生が、
自分たちがやっている研究がどういう社会的結果をもたらすかを知らないで、
研究を続けていくのは無責任だし、甚だ危険なことだと思います。
ですから科学者や理系の学生は、科学技術倫理を含んだ「社会文化リテラシー」、
社会や文化の中に自分の研究を位置づけることが必要です。
この「科学技術リテラシー」と「社会文化リテラシー」という二つの流れがうまく噛み合わなければ、
科学と社会を結びつける回路はできてこないのではないでしょうか。
―野家さん、本日はどうもありがとうございました。