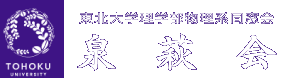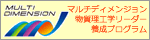泉萩会奨励賞
泉萩会奨励賞について
佐藤繁東北大学名誉教授のご配慮を受けて、以下の要領により泉萩会に学術賞、泉萩会奨励賞を設置する
記
- 泉萩会に、東北大学理学部・理学研究科関係者で、物理科学の分野において特色があり将来性に富む業績を上げた若手研究者を表彰することを目的とした泉萩会奨励賞を設ける。
- 表彰される者の資格は、東北大学理学部・理学研究科の物理系学科・専攻に所属するあるいは所属していた者、及び卒業生とし、年齢は35歳までを目安とする。
- 賞の対象となる研究は、物理科学全般を弾力的に扱い、また技術開発や特許などで社会的な評価のある業績も含む。
- 賞は泉萩会会員の推薦形式による公募とする。但し自薦は認めない。推薦は所定の形式に従った書類によるものとする。また、論文等少なくとも一編を資料として添えること。なお、推薦書および添付論文は、可能であれば、電子ファイルで提出するものとする。
- 前項の一般公募とは別に、物理学専攻2名、地物物理学専攻1名、天文学専攻1名の枠内で各専攻長にも推薦を依頼する。
- 受賞者の選考は泉萩会理事会で行い、総会に報告される。
- 受賞者の表彰式は泉萩会総会時に合わせて行う。また、業績の要旨は会報に掲載されるものとする。
- 本賞決定に要する諸経費は特に計上しない。通常の諸行事のなかで処理される。
- 具体的な選考手続きは理事会が決定する。また、選考内容は公表されない。
これまでの表彰
| 受賞者氏名 | 受賞の業績 | |
|---|---|---|
| 第17回 (R.07) |
MOORE, J. Nicholas 東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
低温における二次元電子系の光学的研究 |
| 栗栖 実 平成29年物理学科卒、 博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
自己生産ベシクル系の創成 | |
| 第16回 (R.06) |
BERNS, Lukas 東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
ニュートリノ振動を用いたレプトンCP対称性の破れに関する研究 |
| 小野 淳 平成26年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
磁性体における光誘起非平衡ダイナミクスの理論研究 | |
| 豊内 大輔 平成24年宇宙地球物理学科(天文)卒、博士(理学)、大阪大学大学院理学研究科 特任助教 |
銀河及び巨大ブラックホールの形成過程に関する理論的研究 | |
| 第15回 (R.05) |
山田 將樹 東北大学学際科学フロンティア研究所 助教 |
電荷を持つブラックホールの球対称なスカラーヘアー |
| 久保田 達矢 平成23年宇宙地球物理学科卒、 博士(理学)、防災科学技術研究所 主任研究員 |
海底観測データに基づく地震と津波と火山噴火現象の総合的研究 | |
| 第14回 (R.04) |
青山 拓也 理学研究科物理学専攻 電子物理学講座 巨視的量子物性研究室 助教 |
強相関電子系におけるスピン・軌道自由度に起因した空間反転対称性の破れに関する研究 |
| 栗田 怜 平成21年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、京都大学生存圏研究所 准教授 |
人工衛星観測データ解析にもとづく宇宙空間プラズマ波動粒子相互作用過程の実証的研究 | |
| 遠藤 晋平 東北大学理学研究科物理学専攻 助教 |
冷却原子気体における量子少数多体問題の理論研究 | |
| 第13回 (R.03) |
Nugroho, Stevanus K. 平成30年度 天文学専攻博士課程修了、自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター 特任研究員 |
可視赤外線の高分散分光の時系列解析による系外惑星の大気組成および構造の解明 |
| 富田 史章 平成25年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、東北大学 災害科学国際研究所(理学研究科兼務)助教 |
2011年東北沖地震に伴う海底地殻変動場の推定とそのモデル化 | |
| 佐藤 隆雄 平成19年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、北海道情報大学経営情報学部システム情報学科 准教授 |
光学リモートセンシングと大気放射伝達計算による惑星大気の研究 | |
| 第12回 (R.02) |
殷 文 平成22年 物理学科卒、博士(理学)、東京大学 物理学専攻 特任研究員 |
インフラトンと暗黒物質のアクシオン的統一の提唱 |
| 那須 譲治 平成18年物理学科卒、博士(理学)、横浜国立大学 大学院工学研究院・准教授 |
多軌道強相関電子系における量子ダイナミクスの理論研究 | |
| 岩井 一正 平成19年宇宙地球物理学科(地物)、博士(理学)、名古屋大学宇宙地球環境研究所准教授 |
地上電波観測に基づく太陽の大気構造およびエネルギー解放過程の研究 | |
| 第11回 (R.01) |
高浦 大雅 平成25年3月 物理学科卒、博士(理学)、 九州大学大学院理学研究院 特任助教 |
QCDにおけるリノーマロンの除去:理論的定式化とαs 決定への応用 |
| 杉山 尚徳 平成22年3月 宇宙地球物理学科(天文)卒、博士(理学)、 国立天文台科学研究部 特任助教 |
宇宙論における銀河解析の新たな手法の開発 | |
| 第10回 (H.30) |
川上 洋平 平成19年物理学科卒,博士(理学)、物理学専攻 助教 |
極短パルスレーザーによる強相関電子系の光誘起相転移と光強電場効果の研究 |
| 木村 智樹 平成17年宇宙地球科学科(地物)卒,博士(理学)、学際科学フロンティア研究所・新領域創成研究部 助教 |
多波長遠隔観測に基づく回転天体磁気圏の物質・エネルギー輸送の解明 | |
| 第9回 (H.29) |
永尾 翔 平成21年物理学科卒、博士(理学)、 東北大学高度教養教育・学生支援機構 助教 |
電磁生成したハイパー核崩壊π中間子分光法による重い水素Λハイパー核の研究 |
| 対馬 弘晃 平成17年宇宙地球科学科(地物)卒、博士(理学)、気象庁気象研究所 主任研究官 |
津波波源逆解析に基づくリアルタイム津波予測手法の開発 | |
| 第8回 (H.28) |
後神 利志 平成22年物理学専攻博士前期課程修了、博士(理学)、大阪大学核物理研究センター 特任研究員 |
7ΛHeおよび 10ΛBe ハイパー核精密分光の成功 |
| 石垣 美歩 平成22年天文学専攻博士後期課程修了、博士(理学)、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 特任研究員 |
銀河系の古成分恒星系の化学動力学に基づく銀河系の形成と進化の研究 | |
| 第7回 (H.27) |
茅根 裕司 平成18年宇宙地球物理学科(天文)卒業、博士(理学)、University of California at Berkeley, Postdoctoral Scholar |
宇宙マイクロ波背景放射偏光Bモードの初測定 |
| 小園 誠史 平成14年九州大学理学部卒業、博士(理学、 東京大学)、理学研究科地球物理学専攻 助教 |
火道流の数値モデリングに基づく噴火機構に関する研究 | |
| 第6回 (H.26) |
佐久間 由香 平成18年お茶の水女子大学理学部卒業、博士(理学)、理学研究科物理学専攻 助教 |
分子集合体からみた生命機能の解明 |
| 石渡 弘治 平成17年理学部卒業、博士(理学)、DESY(ドイツ) PD |
宇宙暗黒物質直接検出のための系統的量子計算 | |
| 第5回 (H.25) |
内田 健一 平成24年物理学専攻博士課程修了、博士(理学)、東北大学金属材料研究所 助教 |
スピン流・熱流相互作用物性に関する研究 |
| 川村 広和 平成15年立教大学理学部卒業、博士(理学、 立教大学)、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 助教 |
時間反転対称性破れの探索のためのレーザー冷却不安定原子生成工場の開発 | |
| 第4回 (H.24) |
鵜養 美冬 平成11年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
ハイパー核ガンマ線分光学の発展とハイパー核精密構造の解明 |
| 第3回 (H.23) |
佐藤 宇史 平成9年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 准教授 |
高分解能光電子分光による銅酸化物及び鉄系高温超伝導体の電子状態の研究 |
| 伊藤 洋介 平成9年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科天文学専攻 助教 |
重力波天文学の理論的研究 | |
| 長谷川 拓也 平成10年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、(独)海洋研究開発機構 研究員 |
太平洋熱帯域における海洋表層貯熱量の研究 | |
| 第2回 (H.22) |
遠藤 基 平成12年物理学科卒、博士(理学)、東京大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
インフレーション宇宙におけるグラビティーノ過剰生成問題の研究 |
| 大槻 純也 平成15年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
近藤格子模型に基づいた強相関 4f 電子系の理論的研究 | |
| 第1回 (H.21) |
是枝 聡肇 平成7年物理第2学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
高分解能光散乱分光による量子常誘電体の低エネルギー素励起の研究 |
| 萩野 浩一 平成5年物理第2学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 准教授 |
低エネルギー重イオン核融合反応の理論的研究 |
第17回泉萩会奨励賞報告(令和7年度)
1.選考経過等
第17回泉萩会奨励賞(令和7年)について、選考委員会(9月22日)において慎重に審議した結果、以下の2名に授賞することを決定した(掲載順位は年齢の若い順)。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | MOORE, J. Nicholas (ムーア・ニコラス) 東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 低温における二次元電子系の光学的研究(Optical studies of two-dimensional electron systems at low temperature) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.授賞理由
ムーア・ニコラス氏は光学的手法を駆使して、二次元電子系(2DES)の撮像と熱量測定の双方に新たな手法を切り拓きました。これにより分数量子ホール(FQH)液体の相転移理解に寄与するとともに、極めて小さな熱容量しか持たないファンデルワールス材料に対しても電子熱量測定の有用性を拡張しました。
半導体ヘテロ構造やファンデルワールス材料に実現される2DESは、新しい量子物質相やその相転移を発見・研究するための豊かな舞台を提供しています。2DESの画像に含まれる空間情報は、独自の知見を与え得ます。ほとんどの2DES では測定が困難である熱容量も、状態密度や低エネルギー励起に直接アクセスする重要な手段となります。
ムーア氏は、FQH 状態におけるスピン相転移において、2DES 全体を横切る縞状の磁区が形成されることを明らかにしました。これにより、通常のFQH 状態では存在しないはずの後方散乱が著しく強められることを明らかにし、20 年ほど謎であった半導体試料を構成する核スピンが偏極される特異な現象のメカニズムを解決しました(論文1)。また、磁区は移動可能であり、その伝搬を制御できること示しました。さらに、2DES に誘起された核スピン偏極を光学的に可視化する手法を開発し、スカーミオンに関連する長距離秩序を持った磁区の形成やダイナミクスの解明に成功しました。
また、ムーア氏はグラフェン中のディラック電子の理論的熱容量を初めて実験的に検証することで、電子熱量測定に成功しました(論文2)。これは過去に例のない低熱容量測定値です。この測定にはピコ秒オーダーの時間分解能を持った熱緩和時間測定を行うことが必要であり、熱雑音温度計測とテラヘルツ周波数での交流光加熱を組み合わせることで可能となりました。これらの研究成果は、測定の技術革新にとどまらず、半導体ナノ構造やファンデルワールス材料研究の両分野に大きな波及効果をもたらすものであると判断できます。
以上により、ムーア・ニコラス氏は泉萩会奨励賞に相応しい業績を挙げていると結論できる。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 栗栖 実(くりす みのる) 平成29年物理学科卒、 博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 自己生産ベシクル系の創成(Creation of a self-producing vesicle system) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.授賞理由
栗栖実氏は、「生命が物質からどのように誕生したのか」という人類の根源的な問題に関して、非平衡ソフトマター物理と合成化学に立脚したアプローチにより、生命のエッセンスである外部から栄養を取り込んで増殖するモデルシステムの創成に成功しました。生命の極めて複雑な実像は、生きているという特異な状態の理解を難しくします。そこで物理学の重要な役割は、生命現象の中で本質的と思われる要素を抽出した単純なモデルを提示し、それらに数理的議論の道を拓くことにあります。栗栖氏の独創的な点は、生命が実際に採用している複雑な分子や化学反応そのものにとらわれずに、むしろ単純かつ少数種の材料から同じコンセプトの分子システムを人工的にデザインすることで、生命の持つ代謝系や自己生産という特徴をボトムアップに再現するモデル実験系をほぼ独力で創成したところにあります。
具体的な実験系設計では、栗栖氏は生命の3つの要素の実現に向けて研究を進めてきました。すなわち、生命の①代謝:外部から取り込んだ原料からエネルギー分子と触媒分子を合成する、②情報処理:触媒分子は個体(ベシクル)を構成する分子を認識し、その構成分子を生産する、③再生産:ベシクルは持続的に成長・分裂する、の3つです。これらを踏まえ、栗栖氏は両親媒性分子AOTを主成分とするベシクルと情報高分子の役割を果たす触媒高分子(PANI-ES)を構成単位として、これら3つの要素を含む人工細胞系を世界で初めて構築しました(論文1)。また栗栖氏は「自己生産して増える」という生命らしさに研究開始当初から一貫して情熱を注いでおり、上記の人工細胞系のほかにも、近年は浸透圧差による膨潤を駆動力として1つの親ベシクルから30-300個もの子ベシクルが次々と出芽型分裂により形成されるという過去に例が無い多産な分裂ベシクル系“Osmotic Spawning Vesicle”の構築にも成功しており、ソフトマターの単純な分子系から如何にして生命らしさが現れてくるのかを熱心に探索し続けています(論文2)。栗栖氏はこれまでにも日本生物物理学会若手奨励賞、日本生物物理学会 & 国際純粋・応用生物物理学連合(IUPAB)賞、東北大学物理学専攻賞(博士)を受賞するなど、これからの生物物理を牽引する若手のホープとして注目されています。
以上により、栗栖実氏は泉萩会奨励賞に相応しい業績を挙げていると結論できる。
第16回泉萩会奨励賞報告(令和6年度)
1.選考経過等
第16回泉萩会奨励賞(令和6年)について、選考委員会(9月30日)において慎重に審議した結果、以下の3名に授賞することを決定した(掲載順位は年齢の若い順)。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | BERNS, Lukas (ベルンス・ルカス) 東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | ニュートリノ振動を用いたレプトンCP対称性の破れに関する研究 (Study of leptonic CP violation using neutrino oscillations) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.授賞理由
我々の住む宇宙には、反粒子から構成される反物質が存在する証拠はなく、宇宙の初期において粒子と反粒子間の対称性の破れ(CP対称性の破れ)により、反粒子は消えてしまったと考えられている。そして、ニュートリノの属するレプトンにおける粒子と反粒子の対称性の破れが、その謎を解く可能性の一つとして脚光を浴びており、ニュートリノで粒子と反対称性粒子間の対称性を調べることが重要と考えられている。そのため、ベルンス・ルカス氏の参加するT2K(茨城県東海村の大強度陽子加速器施設J-PARCで大強度ニュートリノビームを作り、岐阜県飛騨市神岡町に位置する世界最大のニュートリノ検出器「スーパーカミオカンデ」に打ち込む実験)やスーパーカミオカンデの大気ニュートリノ観測実験で探索が進められている。ルカス氏は解析の中心メンバーとして、統計的信頼度90%~94%でのCP対称性の破れの示唆や、未知のニュートリノ質量順序として標準順序を事後確率90%で示唆する結果を得ている(論文1及び3)。
T2K実験は、約500名の精鋭の研究者が参加している実験であり、受賞理由には、ルカス氏の独自の貢献に触れておく必要がある。ニュートリノ振動実験では、多くの系統誤差、振動パラメータ空間の複雑な構造のもと、小数統計に従う限られた観測事象数を用いて感度を最大に保つために膨大な計算が行われている。ルカス氏は、ニュートリノ・フラックスの計算及び振動解析において主解析者として貢献し、系統誤差の削減のほか、解析コードの効率化により振動パラメータの制限を従来の1次元から重要な2次元パラメータ空間全体へ拡張した(論文1)。今後指数関数的に増えると予想される計算量を千分の一以下に抑える簡易な手法を独自に提案し、優位性を理論的に証明した(論文2)。T2K実験による加速器ニュートリノのデータと、スーパーカミオカンデによる大気ニュートリノ観測のデータの初の合同解析を行い、ルカス氏はデータ間の系統誤差の相関を取り入れ、両実験データの統計学的適合度を確認した。また計算時間の大部分を占める大気ニュートリノ振動確率の計算法で数値的安定性の向上及び地球の内部構造をより正確に取り入れる新手法を開発した。この中でCP破れの統計的有意性が本分野にてこれまで過小に評価されていたことを指摘し、CPの破れに対する感度について統計量約1.5倍増加に相当する向上を実現した(論文3)。
以上により、ベルンス・ルカス氏は泉萩会奨励賞に相応しい業績を挙げていると結論できる。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 小野 淳(おの あつし) 平成26年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 磁性体における光誘起非平衡ダイナミクスの理論研究 (Theoretical study on photoinduced nonequilibrium dynamics in magnets) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.授賞理由
小野淳氏は、電場や磁場、温度といった一般的な外場や環境の条件を変えるのではなく、フォトン(光)という電磁波の量子の照射のみで、一般的な外場の変化に対応する効果や、それ以上の新たな効果を生み出すことを目指して、物質の動的な応答の理論研究を行っている。こうした物質の動的応答の理解は、物性の高速制御を可能にするという応用上の意義もあり、現在、理論、実験の両面で盛んに研究が行われ、注目を集めている分野になっている。
遍歴電子と局在スピンが強く結合した系(二重交換系)では、遍歴電子の運動エネルギー利得のために局在スピン間に強磁性的な二重交換相互作用が働く。小野淳氏は、二重交換系の強磁性金属相における遍歴電子を光電場で駆動することにより、平衡状態とは対照的に反強磁性秩序が形成されることを見出した(論文1)。この成果は、強磁性金属相と反強磁性絶縁相の間の双方向変化が光により実現可能あることを意味する。微視的機構を理解するために光照射下の強磁性金属状態における磁気励起スペクトルの解析を行い、非平衡電子分布を反映したストーナー励起過程によって反強磁性的スピン波のソフト化が生じることを明らかにした(論文2)。さらに、この光誘起相転移の過渡状態においては反対称相互作用がない中でも磁気スカーミオンが現れることを示し、三角格子系ではスピンスカラーカイラル状態や120度ネール状態などの非共面的・非共線的な磁気秩序が定常状態として実現することを見出した(論文3)。さらに、反強磁性ディラック半金属を光電場で駆動することで交替磁化方向やバンドギャップの高速制御が可能であることも示している。これらの成果は、光電場で駆動された非平衡状態特有の電子ダイナミクスが磁気秩序の形成や制御を可能にすることの顕著な例を提示しており、今後の研究の進展が期待される。
以上により、小野淳氏は泉萩会奨励賞に相応しい業績を挙げていると結論できる。
6.受賞者3
| 受賞者氏名 | 豊内 大輔(とようち だいすけ) 平成24年宇宙地球物理学科(天文)卒、博士(理学)、大阪大学大学院理学研究科 特任助教 |
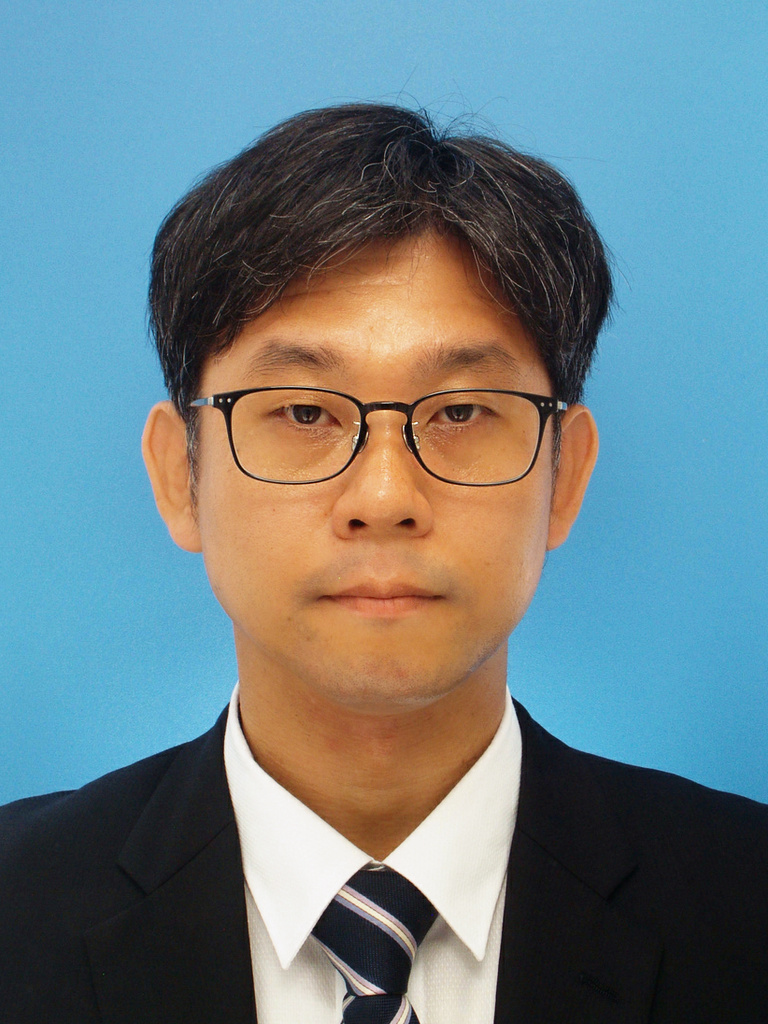 |
| 受賞の業績 | 銀河及び巨大ブラックホールの形成過程に関する理論的研究 (Theoretical Studies on the Formation of Galaxies and Supermassive Black Holes) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
7.授賞理由
ある程度以上の質量を持つ銀河の中心には超巨大ブラックホール(SMBH)が普遍的に存在し、その質量は銀河のバルジ質量と比例していることが知られている。SMBHはガス降着により膨大なエネルギーを解放し、それによる輻射やアウトフローなどのフィードバックを通じて母銀河自体の形成や宇宙進化にも強い影響を及ぼしていると考えられるが、SMBHの起源は不明である。
豊内氏は、SMBHの形成に必要な二つの過程、すなわち「種となるBHを残す大質量星の形成」と「BHの質量成長」のそれぞれについて、降着流の非対称性を考慮した3次元輻射流体シミュレーションを行い、新たな知見と重要な成果を得ている。
論文1は、動力学的に加熱された水素原子からなる母銀河ハロー内の原始星が時間と共にどのように成長するかを調べた結果、初期宇宙で許される様々な星形成環境で形成される初代星(種族Ⅲ)の質量は太陽質量の100~10万倍までの幅広い範囲に分布し、恒星質量と母体ガス雲の密度および温度の間に密接な相関関係が存在することを明らかにした。これは初代星に由来するBHの性質を予言するもので、SMBH形成に向けた初期条件を定めたと言える。論文2は太陽質量の1万倍のBHへのガス降着過程に焦点を当て、降着流の性質がガス密度や金属量に応じて大きく変化することを明らかにし、特定の条件下ではBHが古典的な降着限界を超える速さでガスを降着し、急速に質量成長することを示した。この結果は、初期宇宙に観測されるSMBHの起源解明に向けて、実際にBHが短時間で成長しうることを示した重要な知見である。
ジェームズ・ウエッブ宇宙望遠鏡などによる近年の深宇宙観測によってSMBH形成の初期段階が明らかになりつつあり、宇宙年齢5億年の段階ですでにSMBHが存在することも分かって来た。豊内氏の研究は銀河と巨大BHの形成と共進化、初期宇宙におけるSMBHの起源に関する重要な示唆を与えるものであり、研究会でのレビュー講演を任されるなど分野を代表する若手研究者としても高く評価され今後の貢献が期待されている。
以上のことから豊内氏は泉萩会奨励賞に相応しい研究者であると認められる。
第15回泉萩会奨励賞報告(令和5年度)
1.選考経過等
第15回泉萩会奨励賞(令和5年)について、選考委員会(10月3日)において慎重に審議した結果、以下の2名に授賞することを決定した(掲載順位は年齢の若い順)。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 山田 將樹 (やまだ まさき) 東北大学学際科学フロンティア研究所 助教 |
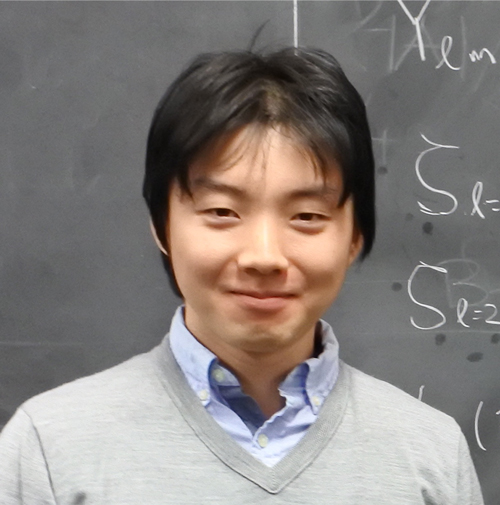 |
| 受賞の業績 | 電荷を持つブラックホールの球対称なスカラーヘアー (Spherically Symmetric Scalar Hair for Charged Black Holes) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.授賞理由
山田將樹氏は素粒子的宇宙理論における数多くのテーマに亘って精力的に研究し続けて来た。特に重要な業績はいわゆる「ブラックホールの無毛定理」とよばれる分野に関するものである。この定理はBekensteinによって提唱された理論であり、ブラックホールの性質には質量,角運動量,電荷以外の特性—hair (髪)とあだ名付けられている—を持たないという主張である。このことは、ブラックホールの性質が素粒子物理学に登場する重粒子数や軽粒子数などの保存量に依存しないことを意味する。この定理は,長距離場として重力場と電磁場のみの存在を前提としているが、その後Mayo とBekensteinにより電荷を持つスカラー場が存在する場合に拡張された(1996年)。山田氏らは,この拡張された無毛定理がスカラー場に対するある仮定に基づいていることを明らかにし,一般にはこれが成り立たないことを示した1)。山田氏らは、さらに、電荷を持ったブラックホールの周りには静的球対称スカラーhairが存在することを実際に示した2)。これらの研究はブラックホールの性質に関する基礎的で重要な成果であり、素粒子的宇宙理論の分野における卓越した成果と言える。これら2件の論文は同じ3名の研究者による共同論文であるが山田將樹氏はその中で主導的立場に位置していたものと認められる。また、2件の論文のうち2番目のものは、3年前に発表されたものであるが、既に30件以上の引用数に到達している。関連して付け加えるならば、山田將樹氏が共著者となっている論文の中には引用数がさらに多いものが20件程存在する。
以上により、山田將樹氏は泉萩会奨励賞に相応しい業績を挙げていると結論できる。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 久保田 達矢(くぼた たつや) 平成23年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、防災科学技術研究所 主任研究員 |
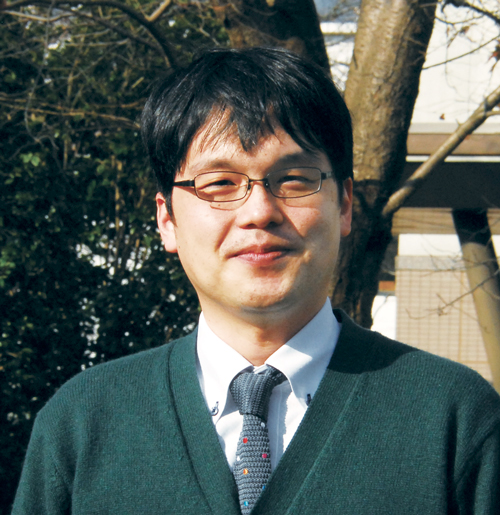 |
| 受賞の業績 | 海底観測データに基づく地震と津波と火山噴火現象の総合的研究 (Comprehensive study on earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions based on seafloor geophysical observations) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.授賞理由
久保田達矢氏は、海域で発生した地震について、海底の観測網で得られた様々な海底観測データに固体-流体結合系の連続体力学の理論を適用して、地震・津波・火山現象の物理メカニズムの理解に向けた研究を行ってきた。
2012年12月7日に、宮城県沖の日本海溝付近の深さ60km付近の太平洋プレート内部で逆断層型のM7地震が発生してから僅か10秒程度の後に、そのごく近傍の深さ20km付近で正断層型のM7地震が発生するという非常に奇妙な地震ペアが生じた。最初の地震は遠地地震波形からなんとか解析できるものの、二番目の地震は波形が最初の地震の波形と重なってしまって、震源も発震機構解も不確定性が大きい。一方、津波波形は一般に浅部の地震に敏感で深部の地震に対しては鈍感なので、その解析によって浅部で生じた二番目の地震の断層モデルを拘束することができる。久保田氏はこのようなアイデアのもと、慎重な解析により、この二つのM7地震の震源断層の位置関係を正確に求めることに成功し、さらにこれらの地震と2011年東北地方太平洋沖地震との関係から、プレート内部の応力や強度の分布の推定にも成功している(論文1)。
また、2022年1月15日に南太平洋トンガ諸島のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山で発生した大規模な噴火により、地球規模で伝播する大規模な津波が発生したが、この津波は通常の津波よりも速く伝播したことが注目された。久保田氏は、この奇妙な津波が地球表面に沿って伝播する大気境界波の一種である「ラム波」によって励起された津波であることを、シミュレーションを用いて明確に示した(論文2)。この論文は噴火から僅か一月足らずで投稿され、その3ヶ月後にScience誌のオンライン版で世界に先駆けて発表されたものである。これは久保田氏が,固体地球と海と大気の3者の相互作用について、長年研究をしてきた経験により実現できたものである。
さらに久保田氏は、地震動と津波が同時に記録されている、2011年東北地方太平洋沖地震(M9.0)の震源域直上の海底圧力計のデータに取り組み、その複雑な波形記録から震源域直上の大振幅の地震波形を取り出すことにも世界で初めて成功している(Kubota et al., 2021)。
以上のように久保田氏は、海底圧力計のデータを独自の視点で解析し、近年、目覚ましい成果をあげて、国内外の学界から注目されており、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると判断される。
第14回泉萩会奨励賞報告(令和4年度)
1.選考経過等
第14回泉萩会奨励賞(令和4年)の公募に対して、推薦書提出が5名あった。選考委員会(9月28日)で慎重に審議し、以下の3名に授賞することを決定した(掲載順位は年齢の若い順)。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 青山 拓也 (あおやま たくや) 理学研究科物理学専攻 電子物理学講座 巨視的量子物性研究室 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 強相関電子系におけるスピン・軌道自由度に起因した空間反転対称性の破れに関する研究 (Study on Spatial Inversion Symmetry Breaking Induced by Spin and Orbital Degrees of Freedom in Strongly Correlated Electron System) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.授賞理由
青山氏は、強相関電子系、とりわけマルチフェロイクス物質を主軸として、高圧下での物性測定を中心に研究を行ってきた。マルチフェロイクス物質は磁気秩序と強誘電秩序が共存する物質であり、磁場による強誘電性の制御など通常とは異なる物性制御が実現できることから、最近急速に研究が進展している。
青山氏は、ダイヤモンドアンビルセルを用いて、これまでほとんど研究例のなかった高圧化でマルチフェロイック物質の強誘電特性を調べることができる測定システムを開発し、マルチフェロイック物質の一つであるペロブスカイト型酸化物TbMnO3 に着目して、高圧力下においてその強誘電特性を調べた。その結果、これまで報告されていた磁気起因強誘電分極の最高値を1桁程度凌駕する巨大な値を示すことを突き止めた(業績論文1)。この成果は、従来は小さいと考えられてきた磁気秩序起因の強誘電分極を、圧力によって大きく増幅できることを示したものであり、磁場・電場によるマルチフェロイック特性の制御のみならず、圧力による制御といった新たな方向性も示すものである。
また青山氏は、ハシゴ型鉄系化合物BaFe2Se3において、従来考えられていていたスピンの自由度だけでなく、軌道の自由度からもマルチフェロイクスが生じうることを示した (業績論文2)。さらに最近では、通常は局在磁性体において適用されるようなマルチフェロイクスの物理を遍歴磁性体へと拡張する研究も展開している。
青山氏のこれらの研究は、マルチフェロイクス物質における新しい機能発現や物性の制御性を開拓した点で、高く評価できる。
以上により、青山拓也氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者と認められる。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 栗田 怜(くりた さとし) 平成21年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、京都大学生存圏研究所 准教授 |
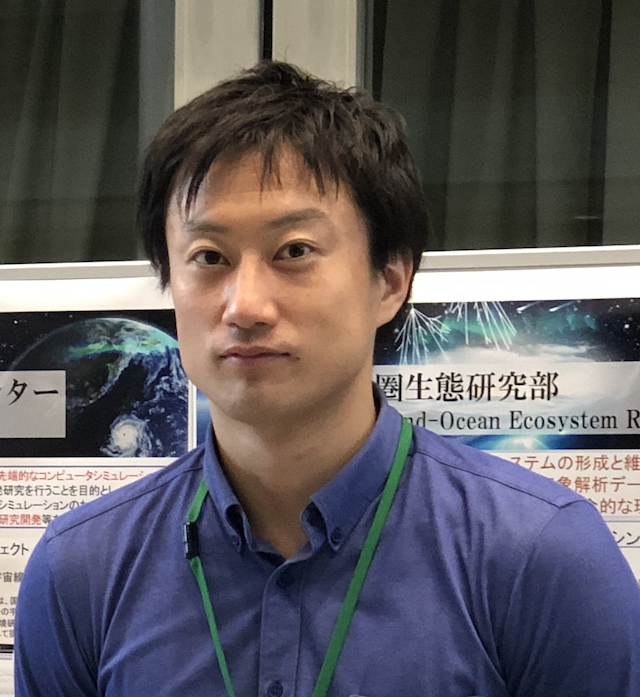 |
| 受賞の業績 | 人工衛星観測データ解析にもとづく宇宙空間プラズマ波動粒子相互作用過程の実証的研究 (Study of wave-particle interactions in the space plasma based on the data analysis of satellites) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.授賞理由
栗田氏は内部磁気圏領域における2つの課題について、これまでの通説を裏づける研究を行ないました。
1. 放射線帯外帯に存在するMeV電子が、時として、急速に減少する現象に取り組みました。方法としては、日本の「あらせ」衛星と米国の「Van Allen Probes」衛星、そして、地上観測のデータを組み合わせて、電磁イオンサイクロトロン波動とMeV電子の相互作用により、数十分以内で放射線帯の高エネルギー電子が消失することを示しました。複数衛星のデータを組み合わせることにより、時間変化と空間変化を分離し、地上観測との比較から、空間スケールを特定することに成功しました。この観測により、放射線帯外帯MeV電子の急速に減少する現象の実像が、押さえられたことになります。
2. プラズマ圏に、VLF 帯のホイッスラーモード波動が励起され、その場の電子サイクロトロン周波数の半分を境界として、上側と下側の 2つに分離して観測されています。その生成理論的では、もともと単一の周波数スペクトルとして励起したものが、非線形波動粒子相互作用によって、上側と下側に分離することが予想されています。栗田氏は、人工衛星によるコーラス波動データを丹念に解析し、コーラスが励起した瞬間のデータの検出に成功し、波動の励起の瞬間では、周波数スペクトルが単一の周波数スペクトルを持つことを明らかにしました。これは、上記の波動粒子相互作用理論の妥当性を決定的とする成果であり、非線形波動粒子相互作用過程の解明に、大きな道筋をつけました。
以上の研究は、通説を裏づけるにとどまらず、次の問題の発見につながる大きな業績です。
栗田怜氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者と認められます。
4.受賞者3
| 受賞者氏名 | 遠藤 晋平(えんどう しんぺい) 東北大学理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 冷却原子気体における量子少数多体問題の理論研究 (Theoretical study on quantum few-body problems in cold atoms) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.授賞理由
ミクロな粒子の運動は量子論に従う。中でも量子論的2体問題については理解が進んでおり、教科書的段階に到達している。他方、数十個からアヴォガドロ数に至る量子論的多体問題についてもこれまでの研究による大きな蓄積がある。ところが、3体から5体程度までのいわゆる少数多体系の量子論は近年に至って始めて目立った進歩が見られた分野である。その進歩には近年パワーが増大した計算機の発達および冷却原子系の実験技術的進歩が寄与している。少数多体系の量子論は冷却原子系や原子核のみならず固体中の少数素励起系も包括されるような研究分野である。少数多体系で特筆すべきは、条件により、エフィモフ状態(V. Efimov1970)と呼ばれる波動関数とエネルギースペクトルが離散的スケール不変性を持つような状態が現れることである。また、エフィモフ状態が現れる条件さえ満たされればスケール不変性のスケールパラメタが個々の少数多体系に依存しないと言う普遍性が存在する。エフィモフ状態は当初同種ボソンの3粒子系の場合について発見されたが、類似の現象は他の少数多体系でも現れ得る。
以下では遠藤晋平氏の業績を紹介する。まず、業績1ではエフィモフ状態を規定する3体パラメタが基本的にはゼロエネルギーにおける2体相関によって決定されることを示した。そして、3体パラメタが有効長を単位としてユニヴァーサルとなるような2体相互作用のふたつのクラスを発見した。そのひとつは超冷却原子系であり、他方は原子核系である。業績2では2種類のフェルミ粒子を2個ずつ合わせた4体系に於いてはエフィモフ状態が現れないことを示した。遠藤晋平氏はさらに共著者とともにエフィモフ状態に関するレビューを著わした(業績3)。このレビューが出版されたのは2017年であるが、既に300件を超える引用数に到達している。このことはこの分野における遠藤晋平氏の立ち位置を表していると言えよう。
以上により、遠藤晋平氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者と認められる。
第13回泉萩会奨励賞報告(令和3年度)
1.選考経過等
第13回泉萩会奨励賞(令和3年)の公募に対して3名の候補者推薦があった。選考委員会(9月27日)において慎重審議した結果、3名の候補者の間で甲乙をつけ難いと判断し、定数オーバーで全員に授賞することを決定した。具体的には、天文学分野のNugroho, Stevanus K. 氏および地球物理学分野の富田史章氏と佐藤隆雄氏(年齢の若い順)の3名である。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | Nugroho, Stevanus K. (ヌグロホ、ステファヌス クリスチャント) 平成30年度 天文学専攻博士課程修了、博士(理学)、自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター 特任研究員 |
 |
| 受賞の業績 | 可視赤外線の高分散分光の時系列解析による系外惑星の大気組成および構造の解明 (Revealing abundance and structure in atmosphere of exoplanets by time-series analysis of high dispersion spectroscopy data in visible and near-infrared wavelength) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.授賞理由
近年、太陽系外惑星の幾つかで大気の存在が報告されている。Stevanus Nugroho 氏は、地上大型望遠鏡を用いて取得した可視光および近赤外線での高分散分光観測結果を時系列的に解析し、親星からの放射や地球大気に由来する放射成分の影響を精度よく除去して系外惑星大気中の分子を検出する手法を確立した。この手法をホットジュピターと呼ばれる木星型巨大惑星のうちで大気の存在と親星の特性が知られている系外惑星の観測データに適用し、惑星大気の組成と構造について新しい知見を得た。
論文1は、すばる望遠鏡と高分散分光器HDSを用いてホットジュピターWASP-33bの昼側大気の観測を行い、惑星大気中にTiO分子が存在すること、さらに成層圏中に温度の逆転層が存在することを世界で初めて明らかにしたものである。
論文2では、ラ・パルマ天文台およびカラル・アルト天文台においてホットジュピターKELT-20b を観測し、この惑星大気中に中性鉄と電離されたカルシウムが存在すること、それらの運動情報から惑星大気が循環していることを明らかにした。また別の系外惑星 WASP-121b と HD149026b のデータ解析では、尤度に基づく Doppler-resolved 分光のデータ解析の手法を確立し、金属分子の発見に貢献している。
系外惑星の大気組成や構造の研究は、今後、加速的に世界各地で進展する段階にある。その中でNugroho 氏が確立した手法は、地上超大型望遠鏡を用いた高波長分散分光観測や衛星を用いた超安定分光観測データに適用され、系外惑星大気の系統的理解と、ひいては生命を宿す系外惑星の探査にもつながるものと期待される。実際、Nugroho氏を含む国際チームは、2021年、すばる望遠鏡にInfraRedDoppler 分光器を搭載してWASP-33b において世界で初めてOH 分子輝線の検出に成功した(Nugroho et al. 2021 ApJ, 910, L9)。OH 分子はホットジュピター大気中で酸素を持つ分子としては組成が最も多く、大気中の酸素量を測定する新しい手法に結びつく研究として高く評価されている。
以上のように、Nugroho氏はすでに国際的な共同研究をリードし顕著な成果を出しており、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると認められる。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 富田 史章(とみた ふみあき) 平成25年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、東北大学 災害科学国際研究所(理学研究科兼務)助教 |
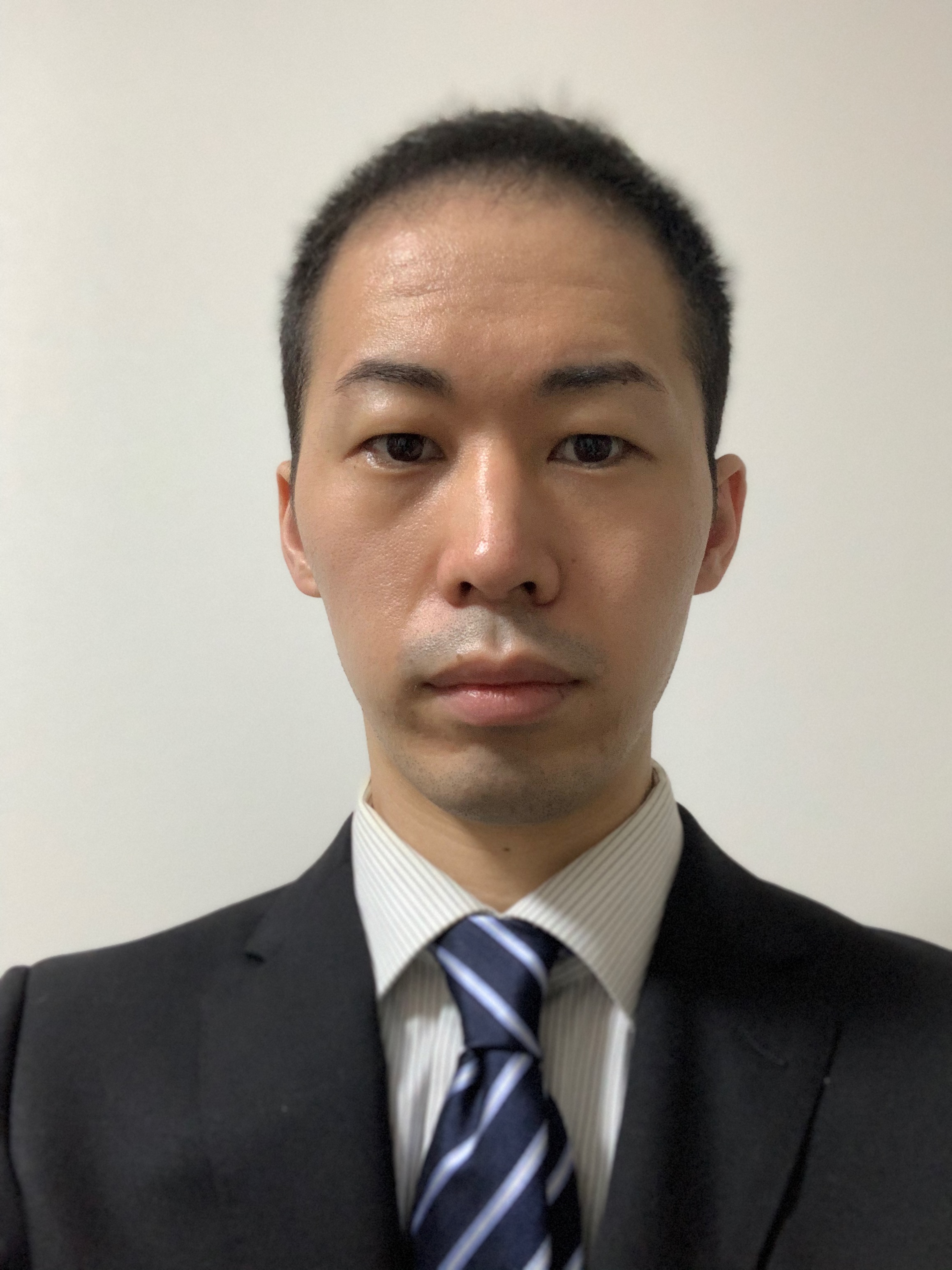 |
| 受賞の業績 | 2011年東北沖地震に伴う海底地殻変動場の推定とそのモデル化(Evaluation and modeling of seafloor crustal deformation associated with the 2011 Tohoku earthquake) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.授賞理由
富田氏は、学部生の頃から海底地殻変動観測の解析に関わり、修士課程に入学してからは観測にも参加して多くのデータを取得し、それらを用いて画期的な論文を発表してきた。特に、2011年東北地方太平洋沖地震(以後、「東北沖地震」と呼ぶ)の余効変動について、海陸の観測データを丹念に解析し、世界中の研究者にインパクトを与える研究成果を上げてきた。
2015年の論文では、東北沖地震後の海溝外側における太平洋プレートの速度変化を解析し、東北沖地震によってプレートの収束速度が速くなったように見えるが、これは東北沖地震後の粘弾性緩和で説明できることを明確に示した。その後、東北沖地震後の余効変動を海底地殻変動データも用いて包括的に解析して2017年に発表した(参考論文1)。これにより、陸上の観測だけではわからない、粘弾性緩和と余効すべりの分離が可能となり、東北日本沈み込み帯における粘弾性モデルやプレート境界の摩擦特性の空間分布を詳細に推定することが可能となった。これは、巨大地震のサイクルを詳細に理解して将来の予測を行う上で、極めて重大な貢献である。
上記の粘弾性緩和は地震時の滑りによる応力変化で生じる。これは逆に言えば、地震後の粘弾性緩和の挙動から地震時の滑りが推定できることを意味する。申請者はこのことを初めて実証して2020年に発表した(参考論文2)。巨大地震発生前に観測網を設置して、地震発生前後のデータを比較すれば、巨大地震の滑り量分布を高精度で推定できるが、巨大地震の発生時期を正確に予測することは現状では不可能なため、巨大地震の発生前から観測を開始することは困難である。富田氏の研究は、地震発生前に観測網が存在していなくても、地震発生後に観測網を展開して長期にわたってデータを取得すれば、地震時の滑り量分布も推定できるということを示した点で画期的であり、今後の国内外での海底地殻変動観測網の展開とその解析に重要な貢献をすると考えられる。
以上のように、富田氏は海底地殻変動観測に基づく巨大地震の余効変動の解析で世界をリードしており、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると判断される。
4.受賞者3
| 受賞者氏名 | 佐藤 隆雄(さとう たかお) 平成19年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、北海道情報大学経営情報学部システム情報学科 准教授 |
 |
| 受賞の業績 | 光学リモートセンシングと大気放射伝達計算による惑星大気の研究 (Study of planetary atmospheres by optical remote sensing and radiative transfer calculation) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.授賞理由
佐藤隆雄氏はリモートセンシングデータから「大気放射伝達モデル」を用いて、惑星大気物理量を抽出するという研究を、一貫して行って来ている。佐藤氏は、大気やエアロゾルによる多重散乱を考慮した惑星大気放射伝達モデルを、太陽放射及び惑星熱放射の双方について独自に開発した。放射伝達コードと、リトリーバル手法開発を駆使した、独自モデルは、すばる望遠鏡の中間赤外観測と日本の金星探査機あかつき観測に応用され、高品質の大気物理量を導出した。
佐藤氏は、すばる望遠鏡に装着された冷却赤外線カメラおよび分光計を用いた地上観測を行い、金星の雲頂構造を調査した(論文1)。観測波長は8.66μmと11.34μm(これらは輝度温度で230Kと238Kに対応)で、地球から金星の日出明暗境界線が見える時期に、200 kmという高い空間分解能で観測した。その結果、金星の雲頂付近の温度構造並びに運動について、以下の重要な調査結果を得た。すなわち、
・南北極域に温度の顕著な日日変動が存在すること、
・両極域の雲模様が同期して西向き移動していること、
・雲層で励起された熱潮汐波(半日潮)が伝搬していること、
・様々なスケールの温度微細構造が存在していること、を示した。
また日本の金星探査機あかつき搭載のIR2カメラが観測した93枚の画像から、金星の昼間の雲頂構造について研究した(論文2)。昼面撮像データから、金星の雲頂高度、スケールハイトが決定され、以下の重要な調査結果を得た。即ち、
・雲頂高度が赤道対称性を持つこと、
・雲頂高度に顕著な太陽地方時依存性がない事、
・低中緯度から高緯度に向かって、雲頂高度の低下がある事、
・山岳波に伴う定在構造の発見と、雲頂高低差が数百m程度であること、を示した。
佐藤氏の以上の研究は、地上と探査機からの金星大気観測の実施と、観測データの高度な処理、そして、金星の雲構造についての数々の発見を行った点で、高く評価される。
以上により、佐藤隆雄氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい研究者と認められる。
第12回泉萩会奨励賞報告(令和2年度)
1.選考経過等
第12回泉萩会奨励賞(令和2年)の公募に対して3名の候補者推薦があった。選考委員会(9月17日)において慎重審議した結果、3名の候補者の間で業績に目立った差がないと判断し、定数オーバーで全員に授賞することを決定した。具体的には、物理学分野の殷文氏と那須譲治氏(年齢の若い順)および地球物理学分野の岩井一正氏の3名である。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 殷 文(いん ぶん) 平成22年 物理学科卒 博士(理学)、東京大学 物理学専攻 特任研究員 |
 |
| 受賞の業績 | インフラトンと暗黒物質のアクシオン的統一の提唱(A proposal of axionic unification of inflaton and dark matter) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.受賞理由
宇宙のきわめて初期に指数関数的な膨張(ビッグバンよりもはるかに急速)の時期があったというのがインフレーション宇宙の考え方である。観測される宇宙が一様等方的であるという事実を理解するために1980 年頃提唱されたこの仮説は,3K の宇宙背景放射のゆらぎの観測など,最近の宇宙論精密観測により,現在では確実視されている。しかし,この膨張を引き起こした物理的な実体が何なのかは不明である。
他方、我々の知っている物質は宇宙の構成要素としてはごく一部であり、いわゆる暗黒物質が既知の物質より一桁多くを占めている。ところが,暗黒物質がいかなる物質かはまだわかっておらず,さまざまな探索実験が進められている。また,素粒子の標準理論には,インフレーションを起こしうる場も暗黒物質となりうる場も含まれない。
さて,量子色力学(QCD)で記述されることが知られている素粒子の強い相互作用は,実験的には空間反転のもとでの対称性(正確にはCP 対称性)を持っているが,理論上は対称性が破れているのが自然である。もし非常に軽いアクシオンという場が存在すれば,なぜ現実には対称性があるのかが理論的に説明できる。このような小質量の場は,素粒子の究極理論と期待されるストリング理論では,容易に出現することが知られており,一般にALP(アクシオン様粒子)と呼ばれる。
従来,インフレーションと暗黒物質は別物と考えられるのが普通であったが,殷氏は,このALP がインフレーションを引き起こしつつ,暗黒物質となりうる可能性があることを見いだした。このためには,ALP の質量とALP の光子との結合の強さの両方が,ある限定された領域にあることが必要である。一般にALP は通常の物質との相互作用が弱いため探索は容易でないが,ALP 探索の次世代実験であるIAXO(太陽から放出されるALPを検出する実験)で検出可能な領域が,この理論で予測される領域と重なっているのは非常に興味深いと言える(業績1,2)。
さらには,この6 月に暗黒物質探索の地下実験"XENON1T"において,ALP 起源かも知れない事象が発見され話題となった。殷氏は,これを上記の理論と比較してよく一致していることを確かめ,注目されている(業績3)。
以上により、殷文氏は泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると認められる。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 那須 譲治(なす じょうじ) 平成18年物理学科卒 博士(理学)、横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 |
 |
| 受賞の業績 | 多軌道強相関電子系における量子ダイナミクスの理論研究(Theoretical study of quantum dynamics in strongly correlated multiorbital systems) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
那須譲治氏はこれまで、軌道自由度をもつ系の電子相関効果に起因する種々の準粒子に関する理論研究において多彩な成果を挙げてきた。
極低温まで磁気秩序を示さない量子スピン液体はP. W. Andersonの提案以降、強相関系分野の最前線の研究課題である。実験的には多くの候補物質が提案されているが、理論的には量子スピン液体形成に重要とされる強い量子多体効果とフラストレーションを同時かつ系統的に扱うことができる手法は著しく制限されており難題のひとつであった。量子スピン液体では、スピンが複数の準粒子に分裂したようかのように振る舞う分数化と呼ばれる特徴的な現象が生じる。那須氏は一連の研究により、創発準粒子がどのように物理量に表れるかを明らかにするとともに実験結果との良い一致も見いだした。この分野の成果に関する代表的論文としては業績1を挙げなければならない。
各種の準粒子の中でも近年特に注目されているもののひとつはマヨラナ準粒子である。マヨラナ準粒子は13年前にキタエフによって提唱された後、それに対する理論的及び実験的研究が進展した。しかしながら、マヨラナ準粒子は中性粒子であり、その存在を明確に示すことが極めて困難である。那須氏らは量子スピン液体を基底状態に持つキタエフ模型に対して、有限温度計算の枠組みを新たに構築することによって、その比熱やスピンダイナミクスなどを近似なしに評価した(業績2)。その結果は熱伝導度テンソルの温度依存性が特徴的な構造を持つことを示しており、キタエフ模型の実験的検証に関する有力な道を開くものである。
那須氏はさらに、トポロジカル量子計算への道筋を拓くと期待されるマヨラナ準粒子に由来した熱ホール効果の半量子化の実証実験にも、理論的補助として参加している。また、キタエフ量子スピン液体の非平衡ダイナミクスやスピン輸送の研究も進めている。
以上により、那須譲治氏は泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると認められる。
4.受賞者3
| 受賞者氏名 | 岩井 一正(いわい かずまさ) 平成19年宇宙地球物理学科(地物)卒 博士(理学)、名古屋大学 宇宙地球環境研究所 准教授 |
 |
| 受賞の業績 | 地上電波観測に基づく太陽の大気構造およびエネルギー解放過程の研究(Studies of atmospheric structures and energy release processes of the Sun by ground-based radio observations) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.受賞理由
岩井一正氏は、東北大学大学院生時代より、電波望遠鏡・電波観測装置の開発研究にかかわってきた。東北大学が保有する口径33メートルの電波望遠鏡を、太陽電波観測に特化する事をめざし、アンテナ給電部、アナログ受信機、偏波計制御部を設計開発した。その結果、150-500MHz 帯域を10ms(ミリ秒)の時間分解能で、太陽電波スペクトル観測できる望遠鏡が完成した。この性能は開発当時、世界最高の性能を出した。扱いの難しいFPGAを太陽電波観測に応用したことが画期的であり、その後の世界の太陽電波望遠鏡の主流となった(論文1)。
岩井氏は、引き続き、日米欧が共同で建設したミリ波・サブミリ波の大型電波干渉計のメンバーとして、太陽観測に加わり、それまでよく分かっていなかった、黒点上空の彩層・コロナ域の温度について研究した。その結果、世界で初めて、黒点上空の彩層・コロナ域の温度構造を明らかにし、活動領域の中心部は、ミリ波では非常に明るいという"黒点増光"を発見した(論文2)。
岩井氏は、名古屋大学所有の電波望遠鏡による惑星間空間シンチレーション観測を基に、コロナ質量放出(CME)を宇宙天気予報に結びつける研究を行った。CMEを含む内部太陽圏のグローバルMHDシミュレーションの結果からシンチレーションを起こす擬似データを算出し、実際の観測データと比較した。その結果、観測データに最も近い擬似データを与えるシミュレーション結果が選ばれ、CME の地球到来を正確に予報出来た。これは、既存のMHD シミュレーションでは10 時間以上にもなるCME 到来時刻誤差を、IPS 観測と「データ同化」の手法を用いることで劇的に低減出来る先駆的成果であり、宇宙天気予報の発展に大きく貢献する結果であった(論文3)。
以上、岩井氏は、科学目的を達成する実験機器開発の能力に卓抜し、さらに、理論シミュレーション技術との融合を図り、宇宙天気予報精度の向上を達成するなど、基礎研究を社会実装する能力に秀でている。選考委員会では、岩井氏提出の論文を、泉萩会奨励賞論文として決定した。
第11回泉萩会奨励賞報告(令和元年度)
1.選考経過等
第11回泉萩会奨励賞(令和元年)の公募に対して、3名の候補者推薦があった。選考委員会(9月20日)において慎重審議した結果、物理学分野の高浦大雅氏と天文学分野の杉山尚徳氏(年齢の若い順)に授与することを決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 高浦 大雅(たかうら ひろまさ) 平成25年3月 物理学科卒 博士(理学)、九州大学大学院理学研究院 特任助教 |
 |
| 受賞の業績 | QCDにおけるリノーマロンの除去:理論的定式化とαs 決定への応用(Renormalon Subtraction in QCD: Formulation and Application to αs Determination) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.受賞理由
QCD は素粒子の強い相互作用を記述する基礎理論である。その相互作用の強さは,理論に含まれる唯一のゲージ結合定数αsにより定まる。どんな種類のクォークもグルオンもαsで決まる大きさで相互作用する。このようにαsの決定は基礎物理定数を定めるという意義がある。
QCD の持つ著しい特徴として,漸近自由性という性質がある。仮想的なクォーク対,グルオン対の真空中での生成消滅などにより,αs はエネルギースケールに依存する有効結合となるが,その大きさは高エネルギーに行けば行くほど小さくなる。これは通常の理論とは逆の傾向である。このため,強い相互作用は高エネルギー領域において摂動展開が有効となる。ハドロンコライダーにおけるハドロンジェット生成などの高エネルギー現象の場合、摂動論による理論計算が実験結果をよく再現し,大きな成功をおさめている。逆に束縛状態である陽子・中性子をはじめとする低エネルギー領域の計算は摂動論では容易でない。クォーク・グルオンの閉じ込めはこの性質と関連している。
クォーク・反クォーク間に働く力のポテンシャルは,短距離では摂動論から導かれるグルオン交換によるクーロン型(αs/r)のポテンシャルであるが,長距離では閉じ込めを反映して距離に比例するポテンシャルとなっている。摂動展開を改良して摂動高次の全次数の寄与のうち主要なものを取り込むことにより,摂動論の適用範囲を広げる努力がなされている。高浦氏の業績は,これを推し進めて,ポテンシャルに対する長距離からくる寄与(リノーマロン)の不定性を除く方法を開発し,2 次の不定性までを実際に除いたポテンシャルを求めている。その結果,かなり長距離まで信頼のおけるポテンシャルを計算することが可能になり,これを格子QCD の数値計算を介してハドロンスペクトル等の実験値と比較することにより,結合定数αsを高精度で決定している。これは強い相互作用の基礎定数決定について,信頼度の高い結果を得たものと評価される。
以上により、高浦氏は泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると認められる。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 杉山 尚徳(すぎやま なおのり) 平成22年3月 宇宙地球物理学科(天文)卒 博士(理学)、国立天文台科学研究部 特任助教 |
 |
| 受賞の業績 | 宇宙論における銀河解析の新たな手法の開発(Development of new methods of galaxy analysis on cosmology) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.受賞理由
宇宙背景放射の観測から、宇宙膨張や空間曲率など宇宙論パラメータが数%以下の精度で決定され、宇宙の進化と構造形成の概観が観測に基づいて詳細に議論できるようになっている。現代宇宙論の次の目標は、超大規模な銀河サーベイと宇宙背景放射のより詳細な偏光観測等によって、宇宙そのものの起源、暗黒エネルギー、銀河形成の詳細を解明することである。杉山尚徳氏の研究は、このどれにも深くかかわっており、特に日本を含め世界中で現在進行中の超大規模銀河サーベイに対する新たな解析手法を提案し実践している。すなわち、銀河分布の3点相関関数の新たな定式化を行うことによって、従来よりも格段に効率的な方法で銀河分布の非ガウス的性質を抜き出すことに成功し、実際にその方法をSloan Digital Sky Survey -IIIおよび日本のすばる望遠鏡銀河サーベイデータに適用して宇宙論パラメータの精度を著しく向上させた(論文1、3)。銀河統計の非線形性は宇宙の加速膨張、したがって暗黒エネルギーにも関係しており、氏の方法は現在、銀河分布解析の標準的方法になって内外から高く評価されている。
論文2で杉山氏が提案したスニヤエフ・ゼルドビッチ効果のフーリエ空間での新たな解析法も、今後の観測的宇宙論において重要になる研究とみなされる。様々な距離にある多数の銀河団についてこの効果を調べることは、宇宙におけるバリオン物質の分布の研究、大規模構造の形成と進化の解明にとって非常に重要であるが、杉山氏の方法はスニヤエフ・ゼルドビッチ効果をより確実に効率よく観測できるため高く評価されている。
以上のように、杉山氏の研究は理論的研究であるが、いずれも実際の観測データを念頭に定式化されて実際に解析に用いられ、観測的宇宙論にとって重要であることが確認されている。理論と観測を直接結び付けることができる稀有な若手研究者であり、今後、研究グループの指導的立場でこれらの作業を進めていくものと期待される。
よって、杉山氏は泉萩会奨励賞にふさわしい研究者であると認められる。
第10回泉萩会奨励賞報告(平成30年度)
1.選考経過等
第10回泉萩会奨励賞(平成30年)の公募に対して、4名の候補者推薦があった。選考委員会(9月13日)において慎重審議した結果、物理学分野の川上洋平氏と地球物理学分野の木村智樹氏(年齢の若い順)を授賞者に決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 川上 洋平(かわかみ ようへい) 平成19年物理学科卒,博士(理学)、現在、物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 極短パルスレーザーによる強相関電子系の光誘起相転移と光強電場効果の研究(Photoinduced phase transition and strong light-field effect driven by ultrashort laser in strongly correlated electron system) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.受賞理由
通常は温度や圧力等の印加で生じる物質の相転移現象と同様に、物理量の急激な変化を強いレーザー光照射で起こすことが可能である。近年のレーザー光やTHz光源、関連実験技術の著しい発展により、光照射による磁性転移、絶縁体金属転移、強誘電転移、超伝導転移などさまざまな光誘起現象が見い出され、理論解析も盛んに行われている。結晶中の電子間相互作用、電子格子相互作用や電子遷移の変化を利用するには、それらのエネルギーに相当するフェムト秒領域の時間測定が必要とされ、超高速時間測定手法の開発が強く求められている。
このような研究背景において川上氏の研究業績は以下のようにまとめられる。1)パルス幅12フェムト秒の超短パルス光源の開発、2)電子格子相互作用の強い有機伝導体のポンプ・プローブ測定実験において、電子の振動と格子の振動との干渉効果が実時間ダイナミクスに現れることを初めて見出した(上記論文(1))。 3)電場成分が10-100MV/cmという非常に強い瞬時電場をともなう光パルスを用いることで、理論的に予測されていた光による電子の運動が抑制される効果「動的局在効果」を実験的に初めて見出した。4)超伝導を示す有機導体において、新しい誘導放射を見出しこれが超伝導転移温度近傍で異常を示すことを明らかにした(上記論文(3))。これらの研究は国内の該当研究分野(光物性、超高速分光)ならびに国外の関係研究者においても高い評価を得られている。
以上のように川上氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい優れた研究業績を上げたものと評価される。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 木村 智樹(きむら ともき) 平成17年宇宙地球科学科(地物)卒,博士(理学)、現在、学際科学フロンティア研究所・新領域創成研究部 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 多波長遠隔観測に基づく回転天体磁気圏の物質・エネルギー輸送の解明(Mass and energy transport processes in rotating magnetospheres uncovered by multi-wavelength remote sensing) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.受賞理由
回転する天体が持つ固有磁場の勢力範囲「磁気圏」の中における、磁化プラズマのエネルギーの解放・輸送過程の理解は、天体周囲の宇宙環境を普遍的に理解する上で、最も重要な課題である。木星は、10時間で高速回転する巨大な回転磁気圏を有し、太陽系で最高エネルギー(<50MeV)のプラズマに満たされており、解放・輸送過程の解明に最適な対象である。
木村氏は、探査機や宇宙望遠鏡を緊密に連携させ、木星磁気圏の巨視的構造を多波長遠隔観測で可視化する事で、この問題の解明に取り組んだ。
審査対象論文で、木村氏は、開発から参加してきた宇宙望遠鏡「ひさき」と、国内外の飛翔体との協調観測を主導し、X線や紫外線のオーロラ観測から、磁気圏の巨視的構造を異なるエネルギーで可視化することに世界で初めて成功した。オーロラ構造の時間発展から、磁気圏外縁部において磁気再結合を介して解放されたエネルギーが、プラズマを数10keV-数10MeVまで加速し、木星方向に急速に輸送することを初めて発見した。これは、自転方向の流れが卓越する回転磁気圏内では困難と考えられてきた、天体方向への急速なエネルギー解放・輸送の存在を明確に示している。
また、オーロラ変動の長期監視から、エネルギー解放が、木星磁気圏の自転、固有磁場、衛星イオの火山ガス、太陽からの高速プラズマ流「太陽風」に起因する4種のエネルギーの蓄積後に発生している事を示唆した。これは、太陽風が唯一のエネルギー源である地球磁気圏とは全く異なるエネルギー解放である事を示している。
これらの論文は、国内外の惑星科学や天文分野の研究者らとの国際・学際共同研究である。木村氏は、異なる国籍・学術的背景をもつメンバーから成るチームを纏めて研究を完遂し、3編の主著論文を発表した。
現在、氏は若手研究者として国際研究グループの指導的立場でこれらの研究作業を進めており、これらの業績から木村智樹氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
第9回泉萩会奨励賞報告(平成29年度)
1.選考経過等
第9回泉萩会奨励賞(平成29年)の公募に対して、4名の候補者推薦があった。選考委員会(10月4日)において慎重審議した結果、物理学分野の永尾翔氏と地球物理学分野の対馬弘晃氏(年齢の若い順)を授賞者に決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 永尾 翔(ながお しょう) 平成21年物理学科卒、博士(理学)、 東北大学高度教養教育・学生支援機構 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 電磁生成したハイパー核崩壊π中間子分光法による重い水素Λハイパー核の研究(Study of 4ΛH hypernucleus with the decay pion spectroscopy of electro-produced hyper竏 nuclei) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
2.受賞理由
永尾翔氏は、高エネルギー電子ビームを利用した電子散乱によるハイパー核研究に取り組んだ。新しく開拓した崩壊π中間子分光法という実験技術により、4ΛH核質量の絶対値(ラムダ粒子の束縛エネルギーに対応)を従来にない高精度且つ高い信頼度で決定した。世界最高精度のハイパー核の質量決定は、同核構造理解に決定的な情報を与えるとともに、ストレンジネス自由度をも含む核力に関する豊富な知見を与える画期的な成果である。独自の実験手法を開発し国際共同研究の中心メンバーとして画期的成果をあげた永尾氏の業績は特筆すべきものである。
ドイツ・マインツ大学の電子加速器からの大強度高エネルギー電子ビームを9Be核標的に照射し、超前方に生成された K+ 中間子を散乱電子と同時検出、9Be(e,e'K+)、することでハイパー核の電磁生成を確認し、生成されたハイパー核からの弱崩壊によるパイ中間子を大型の高分解能電磁石スペクトロメータSpek-A, Spek-Bで検出する。本研究の大きな特徴は、(e,e'K+) 反応により生成され標的中で静止した4ΛHeの2体崩壊過程、4ΛH → 4He+π-、のπ中間子運動量を高精度で測定し、4ΛHe核の質量絶対値を精密に決定したことである。安定核である4He核の質量は既知なので、2体崩壊によるπ中間子の運動量から4元運動量保存則を使って4ΛH核の質量を求めることができる。4ΛH核質量の絶対値決定には、電子ビームのエネルギー絶対値やスペクトロメータの性能を十分な精度で理解する必要があるが、これは必ずしも自明ではない。この困難な作業を永尾氏はマインツ大学の研究グループとともに乗り越え、世界最高精度で4ΛH核の質量絶対値を決定したことは見事である。4ΛH核のような少数系は、核力を与えれば第一原理計算により質量が計算できるため、ストレンジクォークを含むラムダ粒子まで拡張した核力の直接検証が可能という重要な特徴を持つ。
永尾氏は現在、東北大・電子光センターの加速器でのハイパー核の精密寿命測定に向けた研究にも取り組んでいる。このように優れた研究業績をあげ、今後の成長が大いに期待される永尾氏は泉萩会奨励賞にふさわしいと判断する。
3.受賞者2
| 受賞者氏名 | 対馬 弘晃(つしま ひろあき) 平成17年宇宙地球科学科(地物)卒、博士(理学)、気象庁気象研究所 主任研究官 |
 |
| 受賞の業績 | 津波波源逆解析に基づくリアルタイム津波予測手法の開発 (Real-time tsunami forecasting based on tsunami source inversion) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
4.受賞理由
3.11東北沖地震で、気象庁から直後に出された津波警報の津波高は、宮城県で6m、岩手県・福島県で3mであった。実際に来襲した津波の波高と較べてその違いに愕然とするが、それが陸上の短周期地震計データのみを用いた現行の津波警報の予測精度の限界を示している。地震観測センターでは、このような事態が生じることを懸念して、沖合津波データを用いた新しい津波予測手法の必要性を指摘し、新しい手法の導入に向けた第一歩として、東大地震研究所と共同で釜石沖にケーブル式海底地震・津波観測システムを1996年に設置した。このシステムから得られるデータを活用して次世代型とも呼ぶべき新しい予測手法の開発に主として取り組んだのが、大学院生であった対馬弘晃氏である。対馬氏は、博士課程で、沖合津波波形データから津波波源分布を逆解析により推定し、それを基に沿岸の津波波形を予測する手法(tFISH)を開発することに成功した(論文(1))。その成果が認められ、博士課程修了後気象研究所に職を得、その後一貫して予測性能の検証、予測性能向上のための手法改良、社会実装に向けた開発に取り組んできた。その成果は、国内外で広く認められてきたところである。東北沖地震後も手法改良に取り組み、陸上GNSSデータをも用いた予測手法(tFISH/RAPID)を開発し、tFISHの弱点であった地震直後の予測性能を向上させることを可能にした(論文(2))。残念なことに、この予測手法を実用化させる上で基になる沖合津波観測網の展開は東北沖地震の前には実現せず、従って新しい手法の社会実装が実現する前に東北沖地震が起きてしまった。東北沖地震後、その必要性がやっと認められ、懸案のケーブル式地震・津波観測網(S-net)が東日本の沖合に広域に設置された。この観測システムの安定化を待って、漸くにして対馬氏の開発した手法が気象庁の現業に組み込まれる段階に至った。東北沖地震を考えれば遅きに失したとは言え、現業の津波警報として、画期的なシステムであり大きな進展である。
このように、対馬氏は優れた研究成果をあげ,今後の成長が大いに期待されることから、泉萩会奨励賞にふさわしいと判断される。
第8回泉萩会奨励賞報告(平成28年度)
1.選考経過等
第8回泉萩会奨励賞(平成28年)の公募に対して、2名の候補者推薦があった。選考委員会(9月9日)において慎重審議した結果、物理学分野の後神利志氏と天文学分野の石垣美歩氏(年齢の若い順)を受賞者に決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 後神 利志(ごがみ としゆき) 平成22年物理学専攻博士前期課程修了、博士(理学)、大阪大学核物理研究センター 特任研究員 |
 |
| 受賞の業績 | 7ΛHeおよび 10ΛBe ハイパー核精密分光の成功(Success of precision spectroscopy of 7ΛHe and 10ΛBe hypernuclei) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
後神利志氏は,大学院生のときから電子線を用いたハイパー原子核の精密核分光の研究に取り組んできた.米国ジェファーソン研究所において東北大学を中心にした国際共同研究において電子線K+中間子生成反応により世界で初めてハイパー原子核の精密核分光を成功させた.従来は中間子ビームを用いて研究が進められてきたラムダハイパー核であるが,後神氏の行った研究では電子ビームを用いることにより高分解能,高精度の実験が可能であることを示した.
受賞対象に挙げられた論文はともにΛ粒子が原子核を束縛する力(核力)において果たす役割について重要な知見を与えた研究である.1)では10ΛBeハイパー核の精密分光(0.78 MeV分解能)により,これまで乾板による研究やπ中間子ビームを用いて測定された数多くのラムダ粒子束縛エネルギーに対して見直しが必要である極めて重要な情報が報告されている.これまで測定されているミラーハイパー原子核 10ΛBの束縛エネルギーとの違いを指摘しNΛ相互作用の荷電対称性が破れている可能性も指摘している.2)では,7ΛHeハイパー核の精密分光では基底状態および励起状態の観測に成功し、従来よりも高精度の基底状態の束縛エネルギーと世界初の励起状態の束縛エネルギーを求めた.この励起状態の観測成功は6Heの不安定な励起状態がラムダ粒子の「糊的役割」により安定化するという極めて興味深い現象の確認につながる.後神氏は東北大学の大学院生としてジェファーソン研究所に長期滞在し実験の中核として研究に参加した.これらの論文は後神氏の博士論文研究内容の主要な部分となっている.また後期課程修了後も後神氏は京都大学と大阪大学で新たな研究を進めながら,筆頭著者としてその成果を上記論文にまとめた.
このように優れた成果研究成果をあげ,今後の成長が大いに期待される後神氏は、泉萩会奨励賞にふさわしいと判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 石垣 美歩(いしがき みほ) 平成22年天文学専攻博士後期課程修了、博士(理学)、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構 特任研究員 |
 |
| 受賞の業績 | 銀河系の古成分恒星系の化学動力学に基づく銀河系の形成と進化の研究 (Formation and evolution of the Milky Way galaxy based on chemistry and dynamics of the old stellar populations) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
石垣美歩氏は、本学の博士課程(天文学専攻)を終了後、国立天文台に所属し、ハワイ観測所の研究員として、すばる望遠鏡の高分散分光器(HDS)等を用いて金属欠乏星の観測的研究を継続的に行ってきた。現在は暗黒物質など宇宙の根源的謎の解明等を行っている東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)の特別研究員である。上記論文はいずれも世界的に最も権威のある天体物理学会誌に掲載されたものであり、氏が筆頭著者となっている。
恒星内部の核融合で形成される金属(天体物理的な意味で、水素・ヘリウムより重い元素)がない宇宙初期の恒星は種族Ⅲとされているが、これは観測されていない。その理由は種族Ⅲの恒星が大質量星であるため進化が早く極超新星爆発で消失したためと考えられている。氏は添付の論文(1)で銀河系において最も初期に形成された金属量の少ない恒星について、すばる望遠鏡を用いて詳細な化学元素組成を調べ、超新星爆発の理論模型との詳細な比較検討から、種族IIIの星の質量範囲と爆発のメカニズムについて重要な制限を与えた。
石垣氏の現在の研究テーマは銀河の形成史であり、氏の衛星銀河「うしかい座矮小銀河」のすばる望遠鏡による化学組成の分光学的研究も銀河系の化学進化に手掛かりを与える成果の一つである。また、氏は比較的初期に形成された恒星(種族Ⅱ)の集団である球状星団に属する星の組成とその運動を解析することで銀河の化学・力学的な進化 (chemo-dynamical evolution)を調べている。添付の論文(2)が扱っているのは、球状星団「パロマ窶狽T」が銀河の潮汐力によって破砕され引き伸ばされている銀河面を横切る軌道を持った恒星集団の流れ(star stream)である。氏は化学組成の分光分析から「パロマ窶狽T」起源の恒星(母星団と同じ化学組成のもの)を同じ方向に観測される星から分離して、この星流に固有の運動を測定して銀河系の重力場ついて新たな知見を提供している。これは銀河系の重力を支配する暗黒物質ハローの質量・構造を知る重要な手がかりとなるものである。このような直接観測されない種族Ⅲの恒星や、直接観測が不可能なダークマターの研究は銀河の形成史さらには宇宙の歴史を知る上でも重要な現代的課題であり、今後の進展が期待される分野である。
現在、氏は若手研究者として研究グループの指導的立場でこれらの研究作業を進めており、これらの業績から石垣美歩氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
第7回泉萩会奨励賞報告(平成27年度)
1.選考経過等
第7回泉萩会奨励賞(平成27年)の公募に対して、3名の候補者推薦があった。2回の選考委員会(9月8日および10月9日)において慎重審議した結果、天文学分野の茅根裕司氏と地球物理学分野の小園誠史氏(年齢の若い順)を受賞者に決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 茅根 裕司(ちのね ゆうじ) 平成18年宇宙地球物理学科(天文)卒業、博士(理学)、University of California at Berkeley, Postdoctoral Scholar |
 |
| 受賞の業績 | 宇宙マイクロ波背景放射偏光Bモードの初測定 (A First Measurement of the Cosmic Microwave Background B-mode Polarization at Sub-degree Scales) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
茅根氏の研究課題は、宇宙初期のスナップショットとも言うべき「宇宙マイクロ波背景放射(CMB)に関するものである。宇宙の誕生と進化に関するどんなモデルもこの宇宙最古の放射であるCMBの観測を説明しなければならないのでその正確な測定値は宇宙論にとってきわめて重大である。
現在ハーバード大学を中心とする「BICEP2実験」研究グループや欧州宇宙機関(ESA)のグループと並んで、茅根氏が所属する「POLARBEAR実験」グループが精力的にCMBの観測を行っている。このグループは「KEK」や「IPMU」、カリフォルニア大学などの研究者で構成される国際研究グループであり、2012年以来南米チリ・アタカマ高地に建設された直径3.5mのサブミリ波望遠鏡と最先端の超伝導検出器を用いて観測を進め、小さな渦の偏光Bモードの精密測定によって世界で初めてCMBに特殊な重力レンズ効果の測定に成功した。その成果は昨年「PHYSICAL REVIEW LETTERS」(資料1)と「The Astrophysical Journal」(資料2)に発表され、世界的な反響を呼んでいる。この成果は、現在の宇宙の大規模構造の理解の鍵を握るとされる宇宙のニュートリノ質量の精密測定によるダークエネルギーやインフレーション宇宙の解明につながるものである。
茅根氏はグループの一員として理論面の他、「POLARBEAR実験」の心臓部ともいうべき光学系、偏光観測装置の開発に携わってグループの重要な一翼を担い、上記発表論文の主要な部分に寄与している。現在「POLARBEAR実験」は観測範囲と精度を高めるべく「POLARBEAR2」の開発を行っているが、茅根氏はここにおいても指導的役割を務めており、これらの貢献から泉萩会奨励賞に相応しいものと判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 小園 誠史(こぞの ともふみ) 平成14年九州大学理学部卒業、博士(理学、 東京大学)、理学研究科地球物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 火道流の数値モデリングに基づく噴火機構に関する研究 (A study of eruption mechanisms based on numerical modeling of conduit flow dynamics) | |
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
地下深部では高圧のためにマグマの液相に溶解している水などの揮発性成分は、上昇に伴う減圧により気相として析出するため、火道浅部ではマグマの急激な体積膨張が起こり、爆発的な噴火が発生する。一方、マグマ上昇時に揮発性成分が周辺岩体へ散逸する系外への脱ガスが十分進行した場合には、爆発的な噴火は起こらず、溶岩ドーム形成や溶岩流出を伴う穏やかな噴火となる。
小園誠史氏は、このような爆発的・非爆発的といった極端に違う噴火現象が発現するメカニズムを理解するために、火道内マグマ流れの理論的研究を進めた。小園氏は、気液二相流の運動方程式、マグマの発泡、マグマ中に結晶として現れる固相の割合とその成長率に関する方程式を組み合わせるとともに、脱ガス効果をも加味した火道内マグマ流のモデルを構築した(業績1)。数値計算により、マグマ溜まり圧力と噴出率に正の関係を示す安定な定常火道流が生じる場合がある一方で、マグマ溜まりの圧力増の際に噴出率が減少するという、火道流が負性抵抗の性質をもつ場合があることを示した。また、負性抵抗のある場合には、定常的な流れが不安定となり、非爆発的噴火から爆発的噴火への急激な遷移が起こることを明らかにした(業績2)。小園氏は、マグマ溜まり圧力と噴出率の関係と、地質条件やマグマの性質を体系的に分類・整理し、爆発的噴火への遷移条件と観測される現象について解明した。小園氏は、さらに、火道内マグマ流れのモデルを、噴火活動時に得られる地球物理学的多項目観測データや、噴出物の岩石組織、火山ガス・メルト包有物の物質学的分析結果と比較し、
霧島新燃岳2011年噴火の活動理解と定量化を進めた(業績3)。これは、火山噴火予知・火山活動の推移予測方法の新しい枠組みを構築したものとして高く評価されている。
以上により、小園氏は、泉萩会奨励賞にふさわしいと判断される。
第6回泉萩会奨励賞報告(平成26年度)
1.選考経過等
第6回泉萩会奨励賞(平成26年)の公募に対して、3名の候補者推薦があった。選考委員会(9月16日)において慎重審議した結果、物理学分野の佐久間由香氏と石渡弘治氏(年齢の若い順)を受賞者に決定した。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 佐久間 由香(さくま ゆか) 平成18年お茶の水女子大学理学部卒業、博士(理学)、理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 分子集合体からみた生命機能の解明 (Elucidation of Biological Functions Based on Molecular Assemblies) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
物質からどのようにして生命が生まれたのかは、物質科学と生命科学の接点に位置する重大な問題である。生命としての最小限の機能は、1)生命体と外界の接点としての小胞膜(ベシクル)、2)遺伝分子の自己複製、3)エネルギーや物質の代謝、の3点であるが、これらを兼ね備えた仮想的な生命単位を人工的に合成しようという研究は合成生物学と呼ばれる。また、このような生命単位はプロトセルと呼ばれる。
この分野における成果はこれまで極めて限定的であった。佐久間由香氏は、最も単純な膜分子集合体系をプロトセルの物理モデルとして用い、プロトセルの持つ機能の一部を再現する試みを独自に進めてきた。具体的には、膜分子(リン脂質分子)の分子形状と相分離を連携させることにより、2成分ベシクルの膜変形が制御できることを示した。この原理により、佐久間氏はプロトセルの代謝経路に必要なベシクルの孔形成、ベシクル同士の接着、細胞内小器官の再現に成功した(参考資料1)。さらに、プロトセルの最も基本的な特性であるベシクルの自己生産の再現にも成功した(参考資料2)。これらの成果はプロトセルの誕生に関する研究におけるパイオニア的成果と言える。また佐久間氏はこのリン脂質分子の形状がベシクルの自発曲率に及ぼす機構を、中性子小角散乱を用いて世界で初めて示した。一方、これらの物理モデルと本来のプロトセルとの間のギャップを埋めるには、ベシクルに化学反応系を連携させる事が必要である。この点に関しては、ベシクルの化学反応を用いた変形の研究を、フランスのAngelova教授との共同で進めている。
このように佐久間氏は、この分野の発展に大きく貢献しており、泉萩会奨励賞に相応しいと判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 石渡 弘治(いしわた こうじ) 平成17年理学部卒業、博士(理学)、DESY(ドイツ) PD |
 |
| 受賞の業績 | 宇宙暗黒物質直接検出のための系統的量子計算 (Systematic quantum calculation for the direct detection of dark matter in the universe) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
宇宙膨張の問題は宇宙物理学と素粒子物理学の接点に位置する。近年における初期宇宙に関する観測の精密化は素粒子物理学に対し大きなインパクトを与えつつある。中でも、宇宙暗黒物質の存在量が近年高い精度で決定されたことは重要である。宇宙暗黒物質を説明するためには、標準理論を越えた素粒子模型を構築する必要がある。そためには、まず暗黒物質の正体およびその性質を観測結果から正確に読み解く必要がある。
石渡氏は暗黒物質直接検出実験に関する理論予測についての精密な計算を行った。対象となるのは、宇宙暗黒物質と原子核が散乱反応する非常に稀な現象である。石渡氏らは、a) 素過程(クォーク及びグルーオンと暗黒物質の散乱)に対する高次量子補正の計算、b) その素過程からの核子と暗黒物質の散乱振幅の導出、を初めて系統的に行い、従来の結果よりも散乱振幅が大きく抑制されることを見出した(資料1)。この結果は暗黒物質散乱のシグナルがこれまでの実験で不検出であったことと整合する。他方、2012年に発見された質量125GeVのヒッグス粒子の存在は、暗黒物質と核子の散乱振幅をより抑制することを示唆する。そこで石渡氏らは彼らの解析を拡張し、新しい素粒子模型の有力候補である超対称模型において、ヒッグス粒子を含めた精密計算及び将来実験での検出可能性を議論した(資料2)。これらの研究において石渡氏は共同研究者とは独立にすべての解析計算、数値シミュレーションを行った。さらに、計算技法や結果の物理的提示法などに於いて研究を先導した。これらの業績は多くの後続研究を刺激するとともに、今後の暗黒物質直接検出実験において理論予測と観測データを比較する上で重要な成果である。
以上により、石渡氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい判断される。
第5回泉萩会奨励賞報告(平成25年度)
1.選考経過等
第5回泉萩会奨励賞(平成25年)の公募に対して、2名の候補者推薦があった。2回の選考委員会(9月12日、26日)において慎重審議した結果、物理学分野の内田健一氏と川村広和氏(年齢の若い順)を受賞候補者として推薦することとした。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 内田 健一 平成24年物理学専攻博士課程修了、博士(理学)、東北大学金属材料研究所 助教 |
 |
| 受賞の業績 | スピン流・熱流相互作用物性に関する研究 (Study on interaction between spin and heat currents) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
内田健一氏は、東北大学金属材料研究所の斎藤グループに所属し、斎藤英治教授の指導のもとでスピントロニクスの研究分野で基礎的な概念となるスピン流と熱流との相互作用に関する研究に従事し大きな成果を上げた。
スピン流とは上向きスピンの電子の流れと下向きスピンの電子の流れの差で定義され、通常の電流がゼロであっても有限であることが可能であり、スピン角運動量の流れを意味する。スピントロニクスでは、スピン流の生成、制御、検出が重要な課題である。内田氏はこのスピン流ならびにこれと熱流との相互作用について以下の様な大きな業績を挙げた。
a)スピン・ゼーベック効果の発見。金属試料の両端に温度勾配が存在するとき、これに応じて電圧が生じる現象はゼーベック効果(熱電効果)として知られている。内田氏は強磁性金属Ni_81Fe_19において、温度勾配に応じてスピン流を生成させるスピン圧(電流の電圧に相当するもの)が生じることを初めて発見した。これらの研究を契機に、熱によるスピン流生成に関する研究が進展した。
b) 絶縁体におけるスピン・ゼーベック効果の発見。温度勾配によるスピン圧の生成をフェリ磁性絶縁体La_xY_{3-x}Fe_5O_12において見出した。金属、絶縁体にかかわらず磁性体の素励起として存在するマグノンが角運動量を運ぶことがこの現象の起源であることを提唱し、スピン流の本質が電子の流れではないことを実験的に明確にした。
c)音波によるスピン流生成の発見。フェリ磁性絶縁体Y_3Fe_5O_12に圧電素子を接合し磁性体に音波(表面弾性波)を注入することで、スピン圧が生じる現象(音響スピン・ポンピング)を見出した。
このように内田氏はこの分野の発展に大きく貢献しており,泉萩会奨励賞に相応しいと判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 川村 広和 平成15年立教大学理学部卒業、博士(理学、 立教大学)、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 時間反転対称性破れの探索のためのレーザー冷却不安定原子生成工場の開発 (Development of laser cooled radioactive atom factory for the study on the fundamental symmetry) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
川村広和氏は、大学院生のときから、素粒子における基本対称性、特に、時間反転対称性の破れに関する実験研究を進めており、この分野の若手第一人者の1人である。東北大学・CYRICに重点戦略支援プログラム(代表・田村裕和教授)助教として着任した後、電子の電気双極子能率(EDM)探索による時間反転対称性の破れの実験研究を中核研究者として牽引している。川村氏は、特定の原子系で電子EDMが格段に増幅されることに着目して、CYRICの加速器を用いて放射性元素・フランシウムを大強度で生成し、オンラインで引き出してレーザー冷却・トラップして、EDMを測定する事で、これまでのビームを用いた実験の測定誤差の限界を乗り越える事に着想を得た。
川村氏は、この実験の心臓部であるフランシウムを生成するための表面電離型イオン源を開発し、特に、標的の金を高温に加熱して融解したまま核反応を起こす事で引出し効率が大きくなる事を見いだし、国際的にもユニークな融解型標的イオン源の開発を成功に導いた。その結果、フランシウムの引出し効率は、世界のトップレベルを超えて、大強度フランシウム生成を実現した。これらの成果をふまえて、多くの国際会議・研究会において招待講演を行っており、国際的にも高く評価されている。
これらの研究成果をベースに、科研費も若手B(2011年採択)、挑戦的萌芽研究(2013年採択)と、連続して採択されており、その研究アクティビティの高さを示すものである。また、川村氏が実質的に指導した修士課程の大学院生が、2012年度の物理学専攻賞を受賞し、同時に、学振特別研究員に採用され、教育面での実績も非常に高く評価されるものである。
このように研究・教育の両面による優れた成果をあげている川村氏は、泉萩会奨励賞にふさわしい判断される。
第4回泉萩会奨励賞報告(平成24年度)
1.選考経過等
第4回泉萩会奨励賞(平成24年度)の候補者として、物理学専攻長より1名、天文学専攻長より1名、物理学専攻教授より1名の合計3名の推薦があった。2回の選考委員会(9月4日、26日)で慎重審議した結果、鵜養美冬氏(物理学助教)を受賞候補者として推薦することとした。本賞要綱の趣旨、研究の将来性および年齢等を総合的に評価した結果、本年は1名の推薦となった。
2.受賞者
| 受賞者氏名 | 鵜養 美冬 平成11年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | ハイパー核ガンマ線分光学の発展とハイパー核精密構造の解明 (Development of hypernuclear gamma-ray spectroscopy and elucidation of precise structure of hypernuclei) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
鵜養美冬氏は、東北大学のグループが1998年に世界に先駆けて始めたハイパー核精密ガンマ線分光研究のグループに2001年から参加し、一貫してグループの中心としてγ線分光研究を牽引し、発展させた。ハイパー核γ線分光は、鵜養氏の研究を通して、ストレンジネス核物理の最強の手法の一つとして重視されるに至っている。
鵜養氏は博士課程後期から田村裕和教授のグループに加わり、米国Brookhaven研究所でハイパー核γ線分光実験E930を行った。ハード、ソフト両面に秀でた能力を発揮して、グループの中心となって海外での長期にわたる実験を成功させた。その後のデータ解析も単独で行い、論文(1)でΛ粒子・核子間のテンソル力の大きさを初めて解明した。さらに、ハイパー核では初のγγ同時計測の成功(2)、Λ粒子・核子間の全スピン依存相互作用の確定(3)、などの重要な成果を、独創的かつ画期的なアイデアに基づくデータ解析により得た。これらの成果により、2008年度物理学会若手奨励賞を受賞している。最近、鵜養氏はこれらの成果をまとめた物理学会誌の解説記事(vol.67(2012),No.1 14)を執筆したが、この記事は氏がこの分野の第一人者であることを示している。2006年には、J-PARCでの新しいハイパー核γ線分光実験のための実験提案書を田村教授と共同で書き、E13実験として高い優先度で採択された。その後、鵜養氏は、E13のための新型γ線分光装置Hyperball-Jの開発と実験準備を、研究グループを率いて進めてきた。震災などのため、E13実験は遅れているが、明年春には実施見込みとなった。Hyperball-Jはほぼ完成し性能が確認されており、大きな成果が期待される。
このように鵜養氏はこの分野の発展に大きく貢献しており,泉萩会奨励賞に相応しいと判断される。
第3回泉萩会奨励賞報告(平成23年度)
1.選考経過等
第3回泉萩会奨励賞(平成23年度)の候補者として、物理学専攻長より1名、天文学専攻長より1名、地球物理学専攻教授より1名、合計3名の推薦があった。2回の選考委員会(9月9日、16日)で慎重審議した結果、3名とも水準に達してのみならず、分野が異なる3名の間で優劣が付けがたいこともあり、3名を同時授賞として推薦することとした。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 佐藤 宇史 平成9年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 准教授 |
 |
| 受賞の業績 | 高分解能光電子分光による銅酸化物及び鉄系高温超伝導体の電子状態の研究 (High-resolution photoemission study of electronic states in cuprate and iron-based high-temperature superconductor) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
佐藤宇史氏は、これまで光電子分光装置の高性能化に取り組み、エネルギー分解能や最低到達温度において世界最高水準の性能を有する光電子分光装置を建設した。これを用いて、酸化物系高温超伝導体や最近見出された鉄系高温超伝導体の超伝導発現機構ついて以下の重要な知見を得た。
① 電子型高温超伝導体の超伝導ギャップの波数依存性の直接観測[業績1]
電子型とホール型の超伝導機構が同じであるかどうかは、高温超伝導体における基本的問題である。ホール型に比べエネルギースケールが1桁小さい電子型高温超伝導体Nd_{2-x}Ce_xCuO_4の超伝導ギャップの波数依存性の直接観測に世界で初めて成功し、超伝導ギャップが異方的なd(x^2-y^2)波対称性をもつことを明らかにした。
② Bi系高温超伝導体での準粒子構造の発見
Bi系高温超伝導体のブリルアンゾーンのアンチノード付近に現れる準粒子構造(キンク)を世界で初めて見出し、その波数および温度依存性から高温超伝導発現における磁気的相互作用の重要性を指摘した。
③ 高温超伝導の発現に関わる磁気揺らぎ
高温超伝導の駆動力が磁気的なのかそれとも格子振動なのかという基本的問題である。この問題に対して、高温超伝導体に微量の磁性および非磁性不純物を添加して、フェルミ準位近傍のエネルギーバンド分散の変化を高分解能で測定する電子状態の「磁気的同位体効果」を研究し、超伝導に関与するアンチノード領域の電子が磁気的な揺らぎと強く結合していることを見出した。
④ 鉄系高温超伝導体の電子構造[業績2]
鉄系高温超伝導体について、世界に先駆けて超高分解能光電子分光測定を行い、超伝導ギャップや擬ギャップを見出し、その超伝導発現機構解明の手がかりを得た。
以上のように、佐藤氏は、高分解能光電子分光装置の高性能化、および、それを用いた高温超伝導体の研究において大きな貢献をしている。よって、佐藤氏は萩会奨励賞相当と判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 伊藤 洋介 平成9年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科天文学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 重力波天文学の理論的研究 (Theoretical study on gravitational wave astronomy) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
約百年前に提唱された一般相対性理論により存在が予言されている重力波は未だその直接検出に成功していない。この課題は基礎物理学における重要な課題であるのみならず、有望な重力源とされるブラックホール連星や中性子星連星などの相対論的連星系の研究にとっても極めて重要である。現在、世界各地で重力波検出器の建設が予定されており、天文学の重要なフロンティアになりつつある。ここで必要となるのは、相対論的連星系に対して、その運動を理論的に高精度で予測することである。この問題を一般相対性理論で扱つかうことは解析的にも数値計算上でも極めて困難である。この困難を回避する方法としては、ポストニュートン(PN)展開がある。PNは、一般相対性理論のニュートン極限から出発し展開パラメタ (v/c)^2に関して近似の次数を上げてゆく方法であり、問題を質点力学の枠内で扱うことを可能とする:nPN(n次のPN)展開の精度は (v/c)^{2n}である。これまでの研究の場合、2PN方程式までは正確な結果が知られていたが、3PN方程式は不定定数を含んでいた。伊藤氏は、これまでとは別な方法を用いて、3PN方程式を正確に導出することに成功した[業績1]。この成果は氏の博士論文および研究論文としてまとめられた。また、PN展開に関するレビュー論文も執筆している。
伊藤氏はその後、米国の重力波検出プロジェクトにおいて中心的な役割を果たしている研究施設のあるドイツ・マックスブランク研究所および米国ウィスコンシン・ミルウオーキー大学に移って、重力波データ解析の研究を行った。また、単独中性子星からの重力波検出のためのデータ解析や解析パイプラインの信号特性解析などに関して理論面からの寄与をした[業績2]。
以上により、伊藤氏は重力波天文学の理論的研究において優れた研究成果を挙げているのみならず、今後もこの分野の発展に貢献するものと期待される。よって、伊藤氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
6.受賞者3
| 受賞者氏名 | 長谷川 拓也 平成10年宇宙地球物理学科卒、博士(理学)、(独)海洋研究開発機構 研究員 |
 |
| 受賞の業績 | 太平洋熱帯域における海洋表層貯熱量の研究 (Study on Upper Ocean Heat content in the Equatorial Pacific Ocean) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
7.受賞理由
東太平洋の赤道付近で海面水温が上昇するエルニーニョ現象が発生すると、その影響が地球上の様々な地域の天候変化に波及し、大きな気象災害につながることが多い。大気と海洋が密接に関連する代表的な大規模大気海洋相互作用として、多くの研究者の注目を集め、活発に研究されてきた。
長谷川拓也氏は、これまで海面水温に重きを置いたきらいがあったエルニーニョの研究に、海洋表層貯熱量(Upper Ocean Heat Content = OHC)の視点を新たに導入し、数々の新知見を見出してきた。2003年に発表した2編の論文[業績1、2]は、代表的な業績として、多くの研究者に引用されている。まず、業績(1)では、エルニーニョに伴うOHCの正偏差が、エルニーニョ終息後も北半球中線度(北緯15度付近)において西方伝播し、再び西太平洋にもどるというOHC変動サーキットが太平洋熱帯域に存在することを発見した。これは、エルニーニョ発生予測に大いに資するもので、国内外の研究者に大きなインパクトを与えた。
長期間にわたって蓄積された海洋観測資料(主に、水温)を用いて、全球の様々な海域で、10年以上の時間スケールを有する変動現象が発見されるようになった。業績(2)では、OHCを有効に活用し、赤道域にも準十年変動が存在することを新たに見出した。
これらの研究をベースに、エルニーニョ時にOHCが大気に放出される仕方には幾つかの異なった形態があること(2006年発表論文)、北太平洋亜熱帯循環系でもOHC偏差の数十年スケールを持つサーキットがあること(2007年)、南半球ではOHC偏差のサーキットが形成されないこと(2008年)、を明らかにし、活発な研究活動を展開している。
長谷川氏は、OHCという新しい観点から、エルニーニョを含む熱帯赤道域の長周期大気海洋変動研究に新風を吹き込み、この分野の発展に大いに貢献している。よって、長谷川氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
第2回泉萩会奨励賞報告(平成22年度)
1.選考経過等
第2回泉萩会奨励賞の候補者として、物理学専攻長より2名の推薦があった。2回の選考委員会(9月7日、14日)で慎重審議した結果、本年度の泉萩会奨励賞として遠藤基氏(東京大学助教)と大槻純也氏(物理学専攻助教)を推薦することが全会一致で決定された。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 遠藤 基 平成12年物理学科卒、博士(理学)、東京大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | インフレーション宇宙におけるグラビティーノ過剰生成問題の研究 (Study of gravitino overproduction problem in inflationary universe) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
宇宙の地平線問題および平坦性問題と整合し、宇宙論におけるパラダイムとなっているのは、初期宇宙の指数関数的膨張に基礎をおくインフレーションシナリオである。このシナリオは宇宙背景放射の観測によってその存在が明らかになったスケール不変な密度揺らぎによって支持されている。このシナリオでは、膨張の原動力となるインフラトンが指数関数的膨張の後で他の粒子に崩壊することによって、高温高密度の宇宙(火の玉宇宙)が生成される。この過程は宇宙の再加熱化(reheating)と呼ばれる。ところが、素粒子標準理論を包含した量子重力理論が未完成であるため、インフレーションシナリオの枠内でも様々な理論モデルが可能である。また、各モデルは未知のパラメタを含んでいる。量子重力理論の有力な枠組みとしては超対称性を取り入れた超重力理論がある。この理論には、グラビトン(重力子)の超対称パートナーであるグラビティーノ(中性フェルミ粒子)が含まれる。
遠藤氏は超重力理論の枠組みの範囲でインフレーション宇宙に関する理論的解析を行い、宇宙再加熱過程に対する重力の効果を詳細に調べた[業績1, 2]。その結果、定説とは異なり、グラビティーノが一般的にかなり多く生成されることが判明した。この結果と現在の宇宙に関する観測データを比較することにより、各種のインフレーションモデルに含まれる未知のパラメタの値に対して強い制限を与えることに成功した。また、これらの研究はインフレーション後の宇宙再加熱のメカニズム、さらには超対称性の破れの機構の正体に迫る道筋を与えるものと期待される。
以上により,遠藤氏は、発展の初期段階にある素粒子的宇宙論の分野において重要な成果を挙げるとともに、引き続きこの分野を牽引するものと期待される。よって、遠藤氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 大槻 純也 平成15年物理学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |
 |
| 受賞の業績 | 近藤格子模型に基づいた強相関 4f 電子系の理論的研究 (Theoretical study of strongly correlated 4f-electron systems based on the Kondo lattice model) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
結晶中の4f 電子系には強い電子相関が働き、4f 電子は状況に応じて局在性・遍歴性の両方の性質を示す。例えばRKKY 相互作用による磁気秩序状態は4f 電子の局在性の現れである。他方,4f 電子が伝導電子との混成効果により遍歴的性質を得ると,有効質量の大きい重い電子状態が実現する。ところが、重い電子系は理論的研究が極めて困難な強相関量子多体系に属する。そのため、重い電子系の本質を取り込んでいると考えられている近藤格子模型窶箔`導電子の海に局在スピンが周期的に配列されているモデル窶狽ェ理論的研究のターゲットとなっている。候補者は,新しい数値計算手法(連続時間量子モンテカルロ法)を発展させ,これと動的平均場理論を組み合わせて近藤格子模型を研究し,目覚ましい成果を挙げた。以下,上記2論文の成果を分けて説明する。
(1) 近藤格子模型における新たな相の発見
近藤格子模型の安定相として,常磁性状態や強磁性・反強磁性秩序状態が既に知られていたが,伝導電子の密度によっては,電荷密度波(CDW)状態も実現することを明らかにした。このCDW 転移は近藤効果に起因し,基本的な模型で起こりうる新しい秩序という点で大きな意義がある。
(2) フェルミ面に反映する電子の局在性と遍歴性の解明
重い電子系の基本的問題として、フェルミ面の問題がある。すなわち、4f 電子が局在しているか否かにより伝導電子数が変化するので、それがフェルミ面に反映されるのではないかという問題である。しかしながら,その理論的扱いは有限温度効果が特に難しく,これまでは定性的な議論にとどまっていた。候補者は,不純物による乱れと電子相関をともに考慮した理論を構築し,局在から遍歴への移り変わりを,温度と不純物濃度をパラメタとして定量的に明らかにした。
以上のように,大槻氏は、自ら理論的手法を開発し,固体物理学の基本的問題に対して信頼できる結果を出してきた。よって、大槻氏は泉萩会奨励賞相当と判断される。
第1回泉萩会奨励賞報告(平成21年度)
1.選考経過等
選考委員会は9月8日と9月15日の2回開催された。
森田記念賞の候補者は、前年度に推薦された2名のみで、新たな推薦はなかった。他方、泉萩会奨励賞の候補者は、専攻長推薦の3名であった。これら5名の候補者に対して業績等を検討した結果、各候補者の推薦区分を無視して、合わせて適任者を選考することとした。
慎重審議した結果、本年度の森田記念賞には三好由純氏(平成8年地球物理学科卒)、泉萩会奨励賞には是枝聡肇氏(平成7年物理第二学科卒)と萩野浩一氏(平成5年物理第二学科卒)を推薦することが全会一致で決定された。
以上については、10月23日の理事会で承認された。
2.受賞者1
| 受賞者氏名 | 是枝 聡肇 平成7年物理第2学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 助教 |

|
| 受賞の業績 | 高分解能光散乱分光による量子常誘電体の低エネルギー素励起の研究 (A High-resolution Light-scattering Study on the Low-energy Excitations in Quantum Paraelectrics) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
3.受賞理由
是枝氏の受賞理由は、代表的な"量子誘電体"チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)において、理論的に予測されていた第二音波の存在を、実験的に検証したことにあります[業績1,2]。この成果は、この種の物質において「温度の波動」、つまり「熱の固有状態」が存在することを示し、新しい物性研究の道を開いたものと高く評価されます。
同氏は、光散乱、主にブリルアン散乱を用いて物質の低エネルギー励起状態を研究している新進気鋭の若手研究者です。この低エネルギー領域(1000 GHz以下、特に注目するのが100 GHz以下のエネルギー)では、分光装置の分解能が重要な要因となってきます。同氏は、単一モード発振のアルゴンイオンレーザとサンダーコック型のファブリーペロー干渉計を組み合わせた高分解能光散乱分光装置を開発し、使用してきました。本実験では、はじめに、SrTiO3を含むいくつかの物質の低エネルギー励起、特に熱拡散によるレイリー弾性散乱ピークと特異な非弾性散乱ピークの詳細な温度依存性を測定しました[業績1]。この研究から、SrTiO3に注目することになります。さらに、新しい手法として、「フォノン気体」に対して非平衡熱力学方程式から動的構造因子を導き、解析に用いました[業績2]。"測定分解能の向上"、"いくつかの物質による測定"、"新しい解析手法の定式化"と段階を踏んだ努力と成果の積み重ねがこの結果を生んだことは明瞭です。このような継続的な努力は、極めて高く評価されます。
4.受賞者2
| 受賞者氏名 | 萩野 浩一 平成5年物理第2学科卒、博士(理学)、東北大学大学院理学研究科物理学専攻 准教授 |
 |
| 受賞の業績 | 低エネルギー重イオン核融合反応の理論的研究 (Theoretical study on low-energy heavy ion fusion reaction) |
|
| 受賞の対象となった論文 |
|
|
5.受賞理由
萩野氏は原子核物理学における最も基本的な問題の1つである低エネルギー重イオンの核反応について,高精度なモデルを開発するとともに,実験データからポテンシャル形状の情報を取得する道を拓き,さらにその手法を核構造解析に応用するなど原子核反応,原子核構造の統一的理解に多くの功績を挙げております。
クーロン障壁以下の低エネルギー領域における重イオン核反応は量子トンネル効果を通じて進行するため,反応断面積がポテンシャル障壁の形状に極めて敏感で,散乱核の励起すなわち結合チャンネル効果の影響を強く受け,モデル化が困難でありました。萩野氏は,結合チャンネル法に基づく理論的枠組みを検討し,従来の線形結合モデルは不十分で高次の効果が重要であることを見出すとともに,振動励起モードとの結合を含めて高次の効果を考慮する新たな手法の開発に成功しました。これによって,反応断面積の理論的予測精度が大幅に向上するとともに,反応断面積データから変形の符号を含めて原子核のポテンシャル形状を詳細に知ることが可能になりました。また,萩野氏がそのモデルを基礎に開発した計算コードは,世界各地で重イオン核反応データの解析に用いられ,重要な役割を果たしています(業績1)。
さらに萩野氏は,この手法がハイパー核構造の研究等にも応用できることを示すなど,核反応,核構造という従来の枠組みを越えてより幅広い視点から原子核を理解する道を模索し,成果を挙げております(業績2)。
よって,萩野氏の研究は今後の展開が大いに期待され,泉萩会奨励賞に値するものと評価されます。